
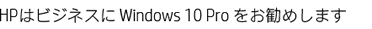
2021.08.20
XR技術やAIを外科手術・オンライン医療に応用
医師の意識改革で社会が医療を担う
医療分野へのデジタル活用が加速している。そんな中、外科医であり実業家でもある杉本真樹氏は、拡張現実(AR)や複合現実(MR)などによる現実空間と仮想空間の融合(XR=Extended Reality)を外科手術やオンライン医療へ応用するためのシステム開発に挑む。最先端のデジタル技術は、医療をどう変えていくのか。遠隔治療の可能性や医療の将来像などについて、日経BP総合研究所上席研究員の大和田尚孝が訊いた。
ベテラン医師の経験とノウハウを研修医がXRで追体験
大和田尚孝(以下、大和田):外科医として活動される傍ら、XR技術を医療に活用するためにHoloEyes(東京・港区)を経営されるなど、マルチに活躍されていますね。
杉本真樹氏(以下、杉本):今は帝京大学沖永総合研究所と会社の仕事が半々ぐらいです。また、週1日は外科医として手術や診察をしています。これからは、一人ひとりが能力を最大限に発揮していくべき時代。医師も同じ場所にとどまらず、様々な領域へ出て新しい刺激やノウハウを積極的に取り入れ、新しい能力を発揮していくべきだと感じています。
大和田:XRのようなデジタル技術を医療現場に導入するメリットは何でしょうか。

日経BP総合研究所 上席研究員 大和田 尚孝 氏
杉本:多々ありますが、私には何か特別なことをしているという感覚はないんですね。デジタル基盤やデータの活用はあらゆる業界ですでに常識となっていて、医療現場も例外ではないというだけです。
医療の世界では、むしろアナログ的なものが重要です。特に外科手術に関しては、ベテラン医師からしか学べない知識やノウハウ、テクニックがたくさんある。そうしたものは、平面的な図面や文字で伝えるより、XRで現実空間に3Dデータを重ね合わせて可視化し、動きを直感的に追体験できるならその方がはるかに習熟が速い。CTスキャンやレントゲンのデータを効果的に可視化したり、コミュニケーションの質を高めたりするうえでもXRのような技術は役立ちます。

ホログラムで空間に人物像を浮かび上がらせることが可能。
大和田:XRのような最先端のデジタル技術を活用すれば、ベテラン医師の技術や経験を若い医師が無理なく直感的に追体験できるわけですね。しかし、手術は人の命に関わる分野です。新しい技術を導入するためのご苦労はありませんでしたか。
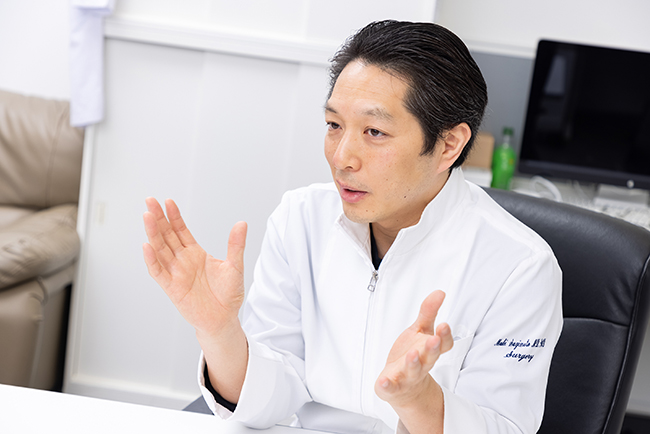
HoloEyes株式会社 共同創業者 COO・CMO 帝京大学 沖永総合研究所教授・イノベーションラボ室長 医師・医学博士 杉本 真樹 氏
杉本:そうですね。医療現場はシビアですから、まず医師にとって安心できなくてはいけません。操作や理解が難しいものも導入できません。ジェスチャーや音声だけで操作でき、インターフェイスもシンプルである必要があります。
幼少時代からデジタル機器に慣れ親しんできた今の若い研修医は、紙で教わるよりXR体験の方を好みます。しかし、教える側のベテラン医師は、必ずしもそうしたものに慣れている人ばかりではありません。
3DやXRのような体験に不慣れな人でも、平面的なモニター内ではなく、VR空間で立体的に捉えられ、自然な動きで直感的に使えるツールが必要です。楽しみながら使えるツールなら、誰でも自然に工夫していくことができます。こうして誰でも立体的な教材も制作できますが、良い教材とは教える側がヒーローになれるもの。教える喜びを体感できるようなものだと感じています。

動脈や静脈など患者の体内にある血管を3Dデータで立体的に確認することができる。
エビデンス以上に実際に使って有意義だと感じてもらうことも重要
大和田:XRに限らず、ネットワークやデジタルを活用した医療は、いまどのくらいのレベルに達しているとお考えでしょうか。
杉本:現在オンライン診療に対応している施設は約2万件といわれますが、ほとんどが電話対応のみのようです。音声だけのコミュニケーションにはミスや誤解も起きやすく、相手の確認や十分な記録も取れないといった課題があります。
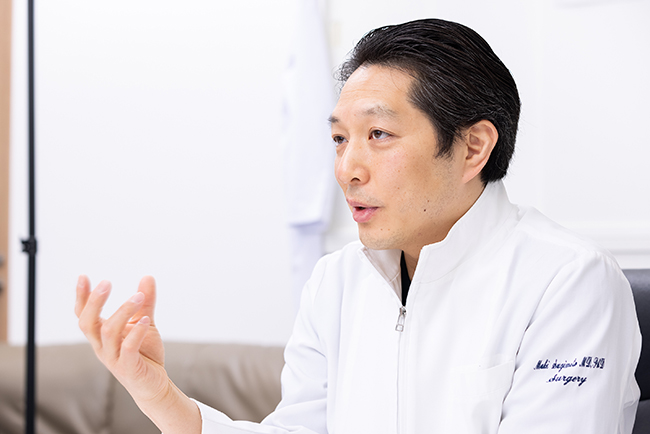
テレビ会議システムも広がりつつありますが、コミュニケーションツールとしては不十分です。高齢者がモニター越しに医師を見ると、単なるテレビ鑑賞に似た感覚に陥り、会話が成立しづらいことも実験からわかっています。そこで、私はモニターの枠を取り払うような体験として、ホログラムで空間に人物像や医療情報を投影しようと考えたわけです。

モニター越しではなくホログラムを使用しまるで直接対面で会っているかのようなコミュニケーションを実現。
また、医師と患者、医師と医師など、1対1のコミュニケーションを脱却し、複数の患者や医療関係者が同時に参加できるような遠隔診療が必要です。患者と家族が一緒に受診したり、その場で複数の医師からセカンドオピニオンを得たりできるようになれば、遠隔診療の価値も高まるでしょう。
大和田:確かに、場所や人数を問わない遠隔コミュニケーションがあれば、遠隔診療も一段と広がりますね。
杉本:患者が普段から親しんでいる場所で遠隔診療を受けられれば、緊張を和らげることができます。また、普段から通っている薬局なども効果的ですね。例えば、すでに薬剤師が患者の血圧や脈を測り、ネット経由で医師にデータを送れば、医師はその場で薬剤を変更したり、投薬法を検討したりされています。ここにオンラインの診療やXRコミュニケーションなどを活用すれば新たな雇用機会も生まれるでしょう。
大和田:そのために越えるべきハードルはありますか。
杉本:いくつかあります。まず、正確な情報を共有していくことです。その意味では、真の専門家でない人がメディアで正確ではない意見を言う昨今の風潮には問題があります。発言の根拠を明確にすべきでしょう。
また、医療の世界では、海外の有名な科学雑誌に載った論文のみをエビデンスとして認めるという風潮が長く続きました。その問題点は、情報の伝達や共有に時間がかかることです。論文の投稿から審査、掲載まで1年ほどかかるケースも少なくないですから。
コロナ禍を見てもわかるように、今は地域に密着した有益な情報をリアルタイムに共有し、すばやく判断、行動すべき時代です。患者も自ら体験したことを、ネットを通じて積極的に発信していくべきでしょう。独りよがりを避けるため、学会や研究会のコンソーシアムなども自分の専門分野を超えて積極的に議論に加わり、客観的な視座を養うとよいと思います。
大和田:そういう意味では、XR技術は論文のようなエビデンスには向かないのでしょうか。

杉本:そうですね。もともと文章での説明が困難ですし、雑誌に論文を投稿しても査読者が理解できないことが多いです。
しかし世の中を見れば、例えばスマートフォンは便利だから普及したのであり、何かエビデンスがあったからではありません。私たちのツールも同様です。エビデンスも重要ですが、まずは実際に使って「まちがいなく患者に有益だ」と思っていただける熱狂的なユーザーを増やしていくことが重要だと思っています。ユーザーが増えて普及が進めば、世の中は必ず変わっていくと思います。
病気を治すその先に、真の医療の社会的価値がある
大和田:テクノロジーの観点から見て、注目されている技術はありますか。
杉本:1つは人工知能(AI)です。すでに医療画像やカルテ情報のデータは膨大にありますが、それらに対する医師の判断を定量化したり、分析するにはAIが有効です。
また、米国で始まっているプレシジョンメディスン(精密医療)にも注目しています。遺伝子や体質の異なる患者一人ひとりに対し、最適化された治療を行うものです。これを支えるツールとして、「遺伝子解析」「画像情報」「生活環境因子」の3つがあり、私たちはその中の画像情報の分野に注力しています。患者個人の臓器や病変の3D座標データを、XRでより直感的に可視化できる技術を開発しています。
大和田:日本の医療現場におけるデジタル活用のレベルはいかがでしょうか。これから必要なことはありますか。

杉本:日本の医療現場におけるデジタル活用は、世界的に見れば進んでいる方だと思います。コロナ禍によってリモートワークが普及し、会社のオフィスと自宅との距離感が近くなりました。同様に、医療機関と自宅との壁も越えられるでしょう。
病院に行かなくても、オンラインで自宅から受診できるようになりました。将来的には、病院という機能はコンビニやオンライン購入などに移行していくでしょう。
そしてこれからは、一般の方がもっと医療を学ぶべきです。
医師や病院などの専門家にすべてを任せるのではなく、患者が自分で選び、決められる。インフォームドコンセントとは本来、そういうコンセプトです。やがて医療と健康生活と社会との線引きが緩まり、最終的には医師が要らなくなる世界が来るかもしれませんね。
大和田:「医療の民主化」とも言えるでしょうか。
杉本:その通りです。テクノロジーの進化とともに、医療や健康維持に必要な要素が生活の中に自然に浸透していくでしょう。すでに、スマートフォンで血糖値や、酸素飽和度を計測できるようになっています。心電図を記録するためにスマートウォッチを装着する人も増えました。データはクラウドに蓄積されていくので、このようなデバイス活用の動きは、今後さらに加速します。

患者にとって健康な状態をゼロとすれば、病気はマイナスの状態です。病院が単に患者を治療して帰すだけでは、いわばマイナスをゼロにしているだけですよね。しかし、医療の社会的価値を考えるのなら、ゼロに戻すのはなく、プラスに引き上げたいものです。ただ病気を治すだけでなく、病気になりにくい身体や生活を指導したり、健康維持に必要な知識やノウハウ、体力を提供するといったウェルネスに取り組み、「前向きに生きようとする心」や「自分に適したライフスタイルの確立」など自発的な健康促進に重きを置くべきだと思っています。
これからの医師は、病気を治して終わりではありません。患者が社会へ復帰し、どう貢献するかまで考えるべき時代が来ています。すでに医療業務がAIに代替される今、医師が専門技術を積み上げることのみをキャリア形成だとする常識は、転換期を迎えているといえます。そのために、医師こそ自ら積極的に意識改革し、医療を超えた社会と関わり、医療を担う社会にどう貢献していくかを患者や健康な人とともに考え、行動していくべきだと思います。

【本記事は2021年6月29日~7月26日、日経ビジネス電子版Specialに掲載されたコンテンツを転載したものです】
海洋プラスティックを使用したノートPC
HP Elite Dragonfly G2
重さ989g、厚さ16.1mm、CNC削り出しのマグネシウムボディーの軽量ビジネスPC。多彩なセキュリティ機能に加え、のぞき見を防止する内蔵型プライバシースクリーン、物理シャッターを備えたカメラ、コラボレーションを促進する全方位マイクなど、ビジネスに必要な全てをエレガントなボディーに備えました。
- Windows 10 Pro
- 第11世代 インテル® Core™ i5 / i7 CPU
- オンボード8GB / 16GB LPDDR4X
- 256GB / 512 GB SSD ストレージ











