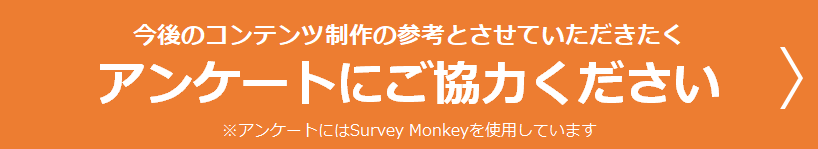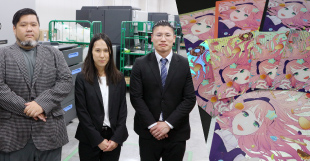2020.04.06
日本となぜ差が開いた?
中国企業から学ぶアフターデジタルの新潮流
顧客価値は「便利さ」から「意味」へシフトする

<Brand Owner>
株式会社 ビービット 東アジア営業責任者 藤井保文氏
<Interviewer>
株式会社日本HP 経営企画本部マーケティング推進部 部長 甲斐博一
日本企業はDXの立脚点を見直すべき
甲斐:今回、ビービットさんが提唱する「アフターデジタル」について、中国市場の最新事例を中心に据えながらお話を伺います。私は今、中国企業は学びの宝庫だと感じていますし、どんどん日本企業との差は開くばかりだと思います。また昨年の反響を受け著書の続編も決定しており、その内容もアップデートされている最中*かと思いますが、改めて本書を通じて読者に伝えたいメッセージを教えてください。
*アフターデジタル 続編(執筆中)
https://www.bebit.co.jp/news/article/20200221/
藤井氏:アフターデジタルで最も伝えたいことは、日本企業のデジタルトランスフォーメーションの立脚点が間違っているのではないか、ということです。中国での先進事例を見てみると、どの企業もデジタルを「顧客提供価値創造」として捉えています。しかし、日本でのデジタルトランスフォーメーションの話題は、システム導入という話題に偏りがち。そもそもデジタルトランスフォーメーションの本質は、顧客との関係性の変化にあると思っています。この点について本書では「製品販売型から体験提供型へ」という言葉で表現しています。
甲斐:私も日本で語られるデジタルトランスフォーメーションには違和感があります。では何故、日本ではこのような誤解が生まれてしまったのでしょうか。
藤井氏:そこには様々な要因が絡んでいると思います。例えば、日本国内では生活インフラが確立されているため、ユーザーのペインポイントが見つけづらいことが挙げられます。中国ではPCが普及する前にモバイルの時代が来てしまったので、その環境の違いもあるでしょう。
そして、環境要因も大きいと思うのですが、日本企業ではデジタルの強みと弱みを理解しようとする方が少ない印象を受けます。中国は人口が14億人もいるので、全ての顧客とリアルの世界で接点を持つこと自体現実的ではありません。しかし、デジタルへと視点を向ければほぼ全員に接触できる可能性があります。それに対して日本は国土も狭く、人口が1億人程度しかいないので、リアルの世界でもある程度タッチすることが可能です。リーチできる数を担保できるところからビジネスを考える上でも、その違いは大きいと思います。
甲斐:日本企業のデジタルに対する理解、という点ではいかがでしょうか。

藤井氏:デジタルとリアルの何が強くて何が弱いのか、十分に理解して連携させている企業が日本には少ないように思えます。
中国の事例を見て優れていると感じるのは、カスタマーサクセスの理論でいうところのハイタッチ・ロータッチ・テックタッチを使い分けている点です。ハイタッチは、一対一の接点をカスタマイズできるもの。ロータッチは一対多ということで、セミナーなどを指します。店舗で考えると、一対一だとしてもテンプレートに沿った接客はロータッチ的ですし、「〇〇さん、また来てくれたんですね」という会話が生まれていればハイタッチ的です。それに対してテックタッチは、一対無限。いつでもアクセスできるオンラインコンテンツがこれに当たります。
OMO(Online Merges with Offline)の事例でよく使われているのは、ハイタッチでユーザーとの信頼関係を築いた後に、テックタッチへユーザーを流すケースです。
そうすると、元々出来上がっていた信頼があるので、ユーザーがその場で使い方を教え合ったり、たくさんの行動を起こしたりしてくれます。デジタルとリアル、それぞれを解像度高く捉えて、強みと弱みを踏まえて連携させながら接触頻度を高めていくことが、今後日本企業に求められてくると思います。
中国市場の潮流は「便利レイヤー」から「意味レイヤー」へ
甲斐:そう考えると、日本企業には「お客様を知りたい」という熱情のようなものが足りていないのでしょうか。おもてなしの精神を語る企業は多いですが、顧客理解に対する必死さは今はあまりないように感じますよね。
藤井氏:そう思いますね。「おもてなし」という言葉は相手との間を読むような意味合いで語られますが、この言葉の本質について、星野リゾートを経営する星野佳路さんは「おもてなしの本質は、自分たちのサービスへのこだわりを顧客に提供することは、悪い言い方をしてしまえば押し付け」と表現されていて、とても印象に残っています。
そもそも西洋と日本ではサービスの意味合いが違います。西洋のサービスは、相手に尽くすサーバント(召使)という意味。一方で、日本のおもてなしの世界では、作法が決められている中で世界観がつくられています。そして、「これが美しい」と決めた上で、その世界観を提示しています。
甲斐:おもてなしはその言葉が持つイメージそのものではなく美徳モラルの共有が事前にある世界で成り立つということですね。そもそも現状における中国と日本では、顧客と企業との関係性も違うようにも思います。
藤井氏:だからこそ、中国の事例がそのまま日本でもうまくいくとは思っていません。やはり、日本らしいアフターデジタルのあり方を考えることが必要です。
甲斐: 中国では、日本の「おもてなし」に見られるような世界観を提示する潮流は生まれないのでしょうか。
藤井氏:なかなか生まれづらいとは思います。ただ、様々な不便が解消されてきたことで、2019年くらいからは「役に立つ」よりも、「意味がある」という価値を追求する流れが出てきています。
これは山口周さんの著書で語られていることですが、乗りやすい汎用的な車よりも、乗りづらいフェラーリのほうが価格もブランド力も高い。そういった意味を追求するような潮流が中国でも生まれてきていることは確かです。
昨年、中国の若者の間では「国潮」ブームが起きていて、自国の伝統文化を取り入れたブランドが支持されています。毎年11月11日に行われる「ダブルイレブン」と呼ばれる商戦でも、中国ブランドの「完美日記(PERFECT DIARY)」が化粧品カテゴリにおいて、国産ブランドで初の売上ランキング1位になりました。中国ブランドが海外ブランドの人気を上回ったことに衝撃を受けた方は多いはずです。
日本人が中国に期待する事例というと、いわゆる「便利レイヤー」にある破壊的な新しいサービスだと思うのですが、僕は今「意味レイヤー」を持った企業に注目しています。
チケットを買うと、もれなく電気自動車が付いてくる
甲斐:中国も便利さにとどまらない価値が求められ始めたわけですね。人間の欲求からすると自然な流れで興味深いです。「意味レイヤー」で注目を集めている企業はあるのでしょうか。

藤井氏:「NIO(以下、ニオ)」というEVメーカーがあります。この企業は”テスラキラー”と呼ばれていて、中国で最もファンマーケティングに成功している会社ともいわれてい
ます。
実際にニオの方から「テスラは鍵を渡すまでが仕事だが、僕らは鍵を渡してからが仕事」という話を聞きました。ニオの車を作っているのはドイツの会社で、デザインを手掛けているのはイギリスの会社なんです。そのため、ニオはほとんど会員コミュニティを運営している会社だといえます。ニオではこの形態を「車を売っているのではなくて、車のチケットを買ってもらっています。そのチケットを買うと、車がお土産として付いてきます」と表現しています。
ニオがしていることは「便利レイヤー」と「意味レイヤー」の両面から考えることができます。「便利レイヤー」では、車のメンテナンスをアプリで呼べる機能が挙げられます。アプリでニオの人を呼ぶと、車をメンテナンスに出してくれたり、充電済の電池を届けてくれてその場で電池交換をしてくれたり、といったサービスが受けられます。他にも、車を空港に置いて海外旅行に行くとして、「何日までに帰ってくるから、それまでに充電しておいて」と頼むと、帰国した時にはフル充電になっている、というサービスも受けられます。
一方、「意味レイヤー」では、ニオのファンが集まる「NIO HOUSE(ニオ ハウス)」というラウンジが特徴的です。ここにはベビーシッティングの部屋も付いているので、子どもを預けて買い物にも行けますし、併設されているカフェでは一日に2~3回イベントを開催しています。このイベントも親子向け、男性・女性向けと様々で、車やサービスについて語り合えるユーザー会もあります。そして、ここには「フェロー」と呼ばれる店員がいて、ユーザーもニオの世界観に共感していることもあり、皆が仲良くなっています。そこではNIOのアプリで連絡先を交換しアプリ上でつながるのですが、ここで驚くのはフェローやユーザーの投稿に100~200近い「いいね!」が付いていることです。ニオの車のユーザー数が2万5000名程度であることを考えると、驚くべきことだと思います。
日本企業でもラウンジを提供している企業はありますが、ここで比べるべきは世界観や品質ではないと思います。ニオが開催するイベントでは、参加者やフェローが友達になり、アプリ上で彼らの投稿に「いいね!」が押され、やがてポイントが貯まり、またラウンジに足を運んでいる。ポイントが貯まればユーザーがオンボードされていって、またイベントに参加し、別の人とつながる。デジタルとフィジカルを上手に組み合わせた体験設計がなされています。OMOの実現ですね。このループが生まれて、より一層のめり込んでいく構造に注目すべきだと思います。
日本企業が学ぶべき先進中国企業のマインドセット
甲斐:ニオの事例にもあるように、中国市場で成功を収める企業は、事業ドメインを明確に決めていないように思えます。一方で、日本企業は予めドメインが決まっている印象ですね。これも産業別に発展してきた日本の各産業があり、またそこにエコシステムも存在しているが故に自分たちのビジネス範囲を決めすぎてしまい、壊せなくなっている気もします。

藤井氏: 中国企業は、価値やミッションでドメインを決めている印象が強いです。そして、ビジネスモデルのつくり方が優れている。人を集める場をつくっておきながら、全然違うところで儲けていたりするので、その仕組みづくりが本当に上手ですね。
でも、中国の企業家の人たちの多くは、「いかに国を良くするか」をしっかり考えています。データを取ったとしても、それをすぐ売上に繋げるよりは、しっかり顧客の体験価値として返していく姿勢を持っているんです。
中国というと管理社会のイメージが強いですが、企業側は新しい価値観を提示しながら、(社会や人々に対して)誠意を持って取り組んでいる印象が強いです。そういった中国企業の姿勢から私たち日本企業が学べる点は多いと思います。
一方で、日本企業に目を向けると「データは財産である」と勘違いしているケースが多いように思えます。データを持っていてもお金がかかるだけなので、それをいかにソリューションとして使える形にするかが大事です。ユーザーには何も還元されず、使用者の信認が得られない形で自社のセールスだけに使っている状態が続くと日本社会の発展が止まってしまうので、今はそのことを懸念しています。
そうした中で、テクノロジーとUXがビジネスの可能性を広げる「アフターデジタル」の世界では、ビジネスパーソンに一定の精神性が求められるようになってくると思っています。
甲斐: 倫理や秩序というと、受身で持たされていくような印象ですが、そうではなくて、もっと内側から沸き起こってくるようなスピリットが必要ということですね。
藤井氏: 提供されたデータをUXやプロダクトといった形でユーザーに還元する「精神性(マインドセット)」、AIやデータをユーザーの価値に換える上で求められる「ケイパビリティ(能力と方法論)」、この2つをビービットでは「UXインテリジェンス」と呼んでおり、DXや新事業に取り組む際には、この2つを持つことが大切です。そして、活動の大義と成果を証明する手段をきちんと準備しながら、挑戦を続けて欲しいと思います。
<インタビューを終えて>

株式会社 日本HP 甲斐 博一
今や中国はビジネスモデルの設計、マーケティングの企画と実践力、そのどれをとっても学びの宝庫である。いつからそうなったのだろう?日本において平成の30年間は失われた30年ととらえるならばなぜ外を見、奢らず外から学ばなかったのだろうと悔いても悔やみきれない。スマートフォンをなぜひとつの小さなコンピュータと消費者と接点をもてる価値ある媒体として定義できなかったのだろうと心から思う。いったい我々は30年間(私が社会に出て仕事をした時間とほぼ一致)何をしてきたのだろうと思う。
でも、デジタルがスマートフォンを媒介として人々の生活に浸透したこの10年間においてデジタル革命を起こせなかった日本企業の大きな問題は嘆いても仕方ない。今は外に学び、変革を仕込む時期である。嘆いていても時間の無駄である。謙虚になり、足りないところを学びながら一つずつクリアしていく時期である。企業活動の原点である顧客理解を徹底的に深めることにデジタル技術は活躍し、マーケティングもそれをもって洞察を深めることから再出発は始まる。
おもてなしは押し付けかもしれない、という言葉は心に残った。それを本当にお客様は望んでいるのか?何を根拠にそのサービスを提供するのか?一人よがりになっていないか?提供したサービスはきちんとPDCAで結果をもってレビューしながら改善されているか?
すべてビジネスの基本である。藤井さんへの取材を終えてビジネスの基本を改めて思い直すにいたった。それをいつの間にか忘れてしまったのではないか?そしてそこにテクノロジーを使う、ということを提案しきれていたか?日本HPの原点でもあるテクノロジーをもって世界中の人々の生活を豊かにする、というパーパスを思い出し、今一度マーケティング業界や印刷業界に価値ある変革を届けたいと今改めて思う。
【本記事は JBpress が制作しました】