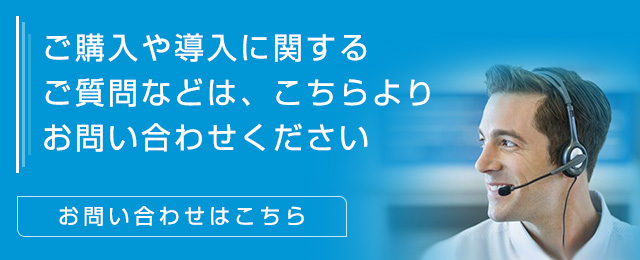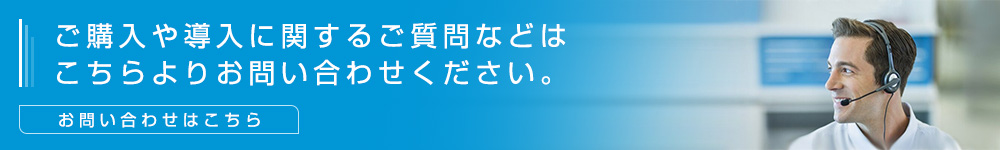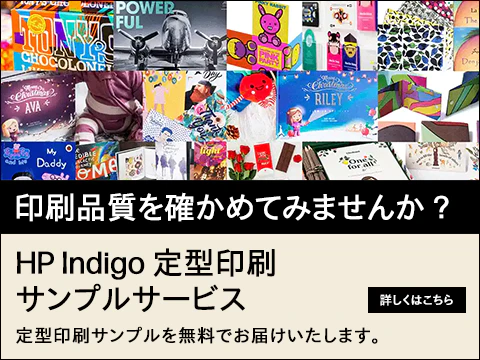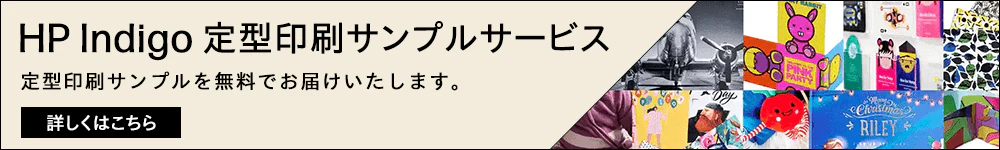淡路島発、世界大手の釣り糸メーカー
ブランド・製造改革・環境で築く持続可能な未来
株式会社ワイ・ジー・ケー(徳島県鳴門市)
釣り糸大手の株式会社ワイ・ジー・ケー(徳島県鳴門市瀬戸町、齊藤隆文社長)は1949年の創業で、68年に現法人を設立。ポリエチレン繊維を編み込む「PEライン」の生産設備で、世界トップクラスを誇り、OEM供給を展開してきた。
2019年には、企業コンセプトを凝縮した自社ブランド「XBRAID(エックスブレイド)」を発売。デジタル印刷や印字とラベリングを同時に行う機器を活用した製造工程改革、環境面への配慮などを製品に反映している。「釣具業界へ新たなソリューションを発信することこそ当社の使命」と語るのは、チーフデザイナーの大塚学氏。同氏の取り組みを軸に、その歩みを追った。
(ラベル新聞社)
多品種展開に潜むラベル在庫の膨大化
HP Indigoとの出会いで改善
同社の歴史は、戦後間もない1949年に「よつあみつりいと中西工場」を創業したことにさかのぼる。創業当初は、地元漁業者向けの網や仕掛け用に、糸をねじり合わせたより糸を製造していた。翌50年には、兵庫県・淡路島の福良に「四編釣糸研究所つりいと工場」を設立。より強く均一な糸を求め、組糸の原型となる4本の糸を編み込む『四つ編み』構造に取り組み、53年にその構造で実用新案を取得した。より糸から組糸への進化こそが、同社の原点となっている。
その後、4本組みを基礎に8本、12本へと多本数化した編み込み糸のブレイドラインへ展開。編み込み技術を高めることで、耐久性と均一性に優れた糸づくりを実現してきた。89年には製造部門を独立させ、現行のワイ・ジー・ケーを設立。以降、日本はもとより世界の釣具業界において不可欠な存在としての地位を確立している。
なかでも同社の強みを発揮してきたのが、PEラインだ。同ラインは、従来のナイロンやフロロカーボンに比べ、軽量で高強度を誇る。かつて一部の釣法に限られる特殊な存在にすぎなかったこの分野に、同社は黎明(れいめい)期から注力し、独自の編糸技術を磨き上げてきた。その結果、高品質路線を貫く姿勢が評価され、世界トップクラスの生産能力を誇るまでに成長。現在では、全8工場による安定供給体制を整え、国内外の釣り愛好者やメーカーから厚い信頼を集めている。

株式会社ワイ・ジー・ケー
チーフデザイナー 大塚 学氏
自社ブランドのパッケージ戦略
同社は長らく、国内外へのOEM供給を主体に展開。しかし、時代の流れとともに、自社ブランドの構築と強化を視野に入れることとなる。そこで、海外進出を見据え商標取得をしていたXBRAIDのリブランディングに着手。このプロジェクトを担ったのが大塚氏で、ロゴのフォント刷新などを行い、海外に先駆け国内市場で販売を開始した。
大塚氏は、企業や製品ブランディングに加え、発注業務から各種ソリューションの推進までを幅広く手がける。自社ブランドの構築では、当時釣り糸外装の主流だったクリアケースに替え、いち早く紙箱を採用。さらに、メタリック紙やエンボス加工などさまざまな加飾を施し、ユーザーが手に取った際の質感までを追求した。これが、自社ブランド浸透のカギへとつながる。
高加飾を施した紙器戦略により、店頭棚における消費者の目線位置を中心に、全体の3分の1を占める大量陳列が可能となった。その背景には、「きらびやかな紙箱を数多く並べれば、売場全体が華やかになる」という大塚氏の発想がある。棚割を描き、売場に馴染みながらも最大限の訴求を行えるデザインを起こしたことで、安定的な棚の確保とブランド浸透の後押しにつながった。
発売直後にコロナ禍という逆風にさらされながらも、このように刷新した華やかな外装は、消費者の認知を獲得。自社ブランドの知名度拡大へとつながっていった。その象徴が、主力製品の「SUPER JIGMAN」だ。同製品は、船で沖合に出て金属製の疑似餌(ルアー)を用い、ブリやカンパチなどの大型魚を狙う“オフショアジギング"専用に開発されたPEライン。高強度と信頼性が評価され、国内外の釣り愛好者から支持を集めてきた定番商品であり、現在では同ジャンルを代表する製品として、確固たる地位を築いている。


ラベル管理の課題 デジタル印刷で改善
高加飾の紙器により、ブランドの確立を実現した同社。しかしもう一つ、釣り糸の販売に欠かせないのが〝商品ラベル〟だ。釣り糸ラベルには、「長さ」「太さ」「強度」の3情報を必ず明記する必要がある。さらに、釣り人のニーズは年々細分化。同一商品でもサイズや色違いを含めれば、数百種類におよぶこともある。OEMの世界対応品であれば、1規格で1000種に達するケースも。このような状況から、ラベル調達を一手に担う大塚氏は「まるでラベルの上で踊っているような感覚」と、日々の業務を語る。
ラベルの初回発注は、各種類2000巻ずつであっても、リピート時には、売れ行きに応じて数量を調整しなければならない。コンベンショナル機での印刷では版代がかかるため、1ブランド多品種のコスト計算は複雑を極め、業務負担は非常に大きなものとなっていた。この状況を改善したのが、約10年前のデジタル印刷機「HP Indigo」との出会いになる。

従来の製造工程では、コンベンショナル機で前印刷したラベルに、釣り糸の太さや強度などを熱転写プリンタで追い刷りする必要があった。しかしデジタル印刷では、版代の計算が不要になっただけでなく、1巻2000枚のラベルを「1号は300巻、2号は400巻、5号は100巻」といった形で自由に組み合わせて発注でき、納品もスピーディーに。近年では、担当するラベル印刷会社に在庫一覧表を渡し、「減っている種類を製造してください」と依頼する体制も整ったという。
1ジョブあたりの発注量としては少量でも、月単位でまとめると大ロットかつ高額となる同社のラベル需要。コスト管理の観点から膨大な在庫を抱えていた現場は、デジタル印刷の活用により在庫圧縮が進み、生産効率やコスト面でも着実な改善が図られていった。
TOPPANインフォメディア株式会社の「プリンターラベラー」で小ロット品種で在庫圧縮を実現「プリンターラベラー」印字と同時貼付で改善
ある企画でパッケージに紙袋を採用した際、ラベルが仕上がった時点で、ラベラーの選定を失念していたことに、大塚氏は気づいた。通常は包装ラインに上貼りラベラーを組み込んでいるが、この企画品は製袋済みで納品されるため、手差しでのラベル貼付が適していたという。
急遽ラベラーを模索する中で、大塚氏はTOPPANインフォメディア株式会社(東京都港区芝浦、堀正史社長、以下TIM)のサイトに適合しそうな機種を発見し、その場で契約。20年のこの案件が、TIMとの最初の取引となった。
この出会いをきっかけに、同社との関係は次の展開を迎える。前述の打ち合わせ時に、大塚氏はラベルの印字と貼付を1台で同時に行うTIMの「プリンターラベラー」に気づき、これについても即契約。これが、現在の業務改善へとつながることとなる。
「ラベルの在庫が工場内の至るところに積み上がっていたため、それらを圧縮するお手伝いができればと思った」と当時を振り返るのは、TIM第二営業本部の山浦大勧氏。現在、同機は、鳴門工場と北島工場の各1ラインで2台ずつ稼働し、ラベル在庫圧縮に大きく寄与している。
山浦氏は「顧客のお困りごとに貢献できたことが嬉しい」と語り、大塚氏や現場との関わりを大切にする。さらに、TIMは、導入済みの「HP Indigo 6900」により、前印刷のラベル納品も担い、同社の効率化を支えている。
ワイ・ジー・ケーのラベル運用は、これまでに2段階で改善されてきた。
第1段階は、コンベンショナル機での印刷からデジタル印刷機への切り替えによるコスト・工程数・在庫の低減だ。しかし、ロールラベルの掛け替え時にロスが発生するため、総在庫枚数の把握が困難になるという課題が残っていた。
そこで第2段階として、プリンターラベラーを導入。発注数量が少ない品種に関しては、前印刷したラベルに、必要な数字を印字し同時にラベリングも行えるため、在庫圧縮と生産性向上の実現をさらに後押しした。熱転写リボンの無駄が発生しない機械ワークのよさもあいまって、齋藤社長の評価は非常に高いという。
釣り糸ラベルにおける可変印字の対象は、糸の長さ、太さ、強度を示す3つの数字だ。同社では、デザイン統一のため、パッケージと同じフォントをTIMに依頼し、プリンターラベラーに対応させている。運用は上々で、今後は数字フォントの追加により、他の品種へも展開する計画だ。

こうした取り組みは、海外市場のトレンドとも一致しているという。米国では、釣り糸ラベルの多くが印字対応だそうで、現地展示会を視察した齊藤社長は「当社のやり方は世界標準に沿っている」と確信。国内外のブランド展開を行う同社にとって、プリンターラベラーの採用を後押しする要因ともなっている。
環境対応含め業界へソリューション提案
同社は、環境配慮にも力を注ぐ。紙箱や紙袋などの紙包装を積極採用し、いずれもFSC認証紙を使用するなど、資材調達の段階からサスティナビリティーを重視。パッケージには認証マークを表示し、ユーザーに環境への取り組みを示している。
ラベルについても環境対応を推進。従来のポリエチレンラミネート剥離紙から、大王製紙のダイレクトグラシンの剥離紙に切り替え、水解性粘着剤使用の粘着紙を採用した。さらに、剥離紙を回収して段ボールへと再生するスキームも展開。これにより、従来リサイクルが難しかった剥離紙に加え、粘着紙の紙管や段ボールも再資源化が可能となった。将来的には、プラスチックスプールの回収・再生にも取り組む計画だ。
パッケージの刷新は、ブランド価値の向上だけでなく、環境対応にも結びつく。実際、同社は釣り糸パッケージの紙器化でブランド訴求に成功しただけでなく、多品種ラベルにHP Indigoなどデジタル印刷を活用。さらにTIMのプリンターラベラー導入により、小ロット多品種においてラベル在庫の圧縮と生産効率化を同時に実現した。

「市場シェアを追うよりも、社内体制を整え、持続可能な社会の仕組みを築くことが大切。強いブランドは、その先に自然とついてくる」と大塚氏は語る。業界をリードする企業として、常に新しいソリューションを発信していく責務があると考える同社の姿勢が端的に表れている。
課題解決のためのシステムや機器を模索し、時代に即した最良の選択を柔軟に採り入れてきた取り組みは、まさにワイ・ジー・ケーの礎だ。世界の釣り糸大手は、効率化とサスティナブル経営を両輪に、次なる成長へと歩みを進めている。
参考リンク
釣り糸メーカー株式会社ワイ・ジー・ケーのブランドサイト「XBRAID」 https://xbraidygk.jp/
TOPPANインフォメディア株式会社 https://www.toppan-im.co.jp/
【本記事はラベル新聞株式会社が制作しました】