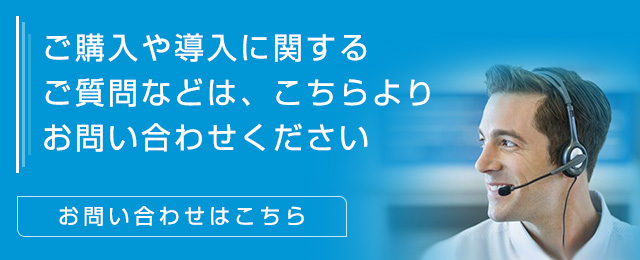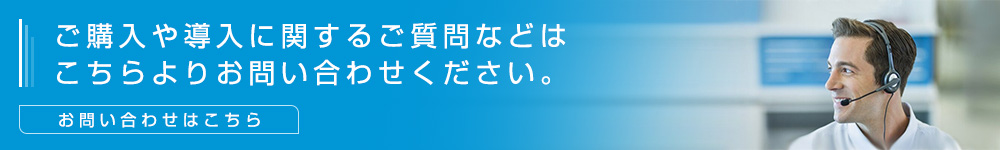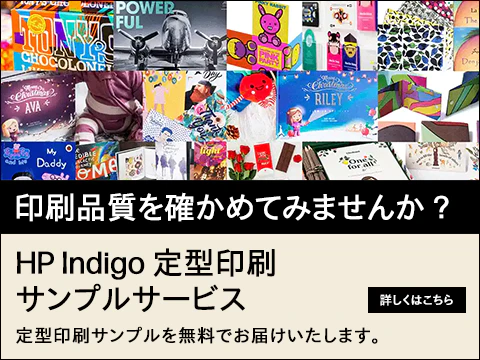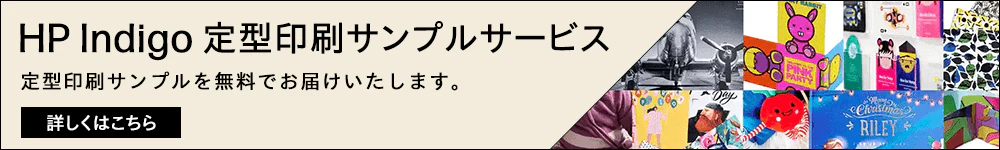軟包装印刷の再定義
──── 消費者ニーズとサステナビリティに応えるデジタル印刷
印刷の再定義 ── デジタルが変える業界の常識と未来
印刷業界は今、かつてない構造変化と技術革新の真っただ中にある。
大量生産・低価格競争という旧来の常識はすでに限界を迎え、求められるのは「柔軟性」「付加価値」「環境対応」といった新たな競争軸である。
その中心にあるのが、デジタル印刷という選択肢だ。
版を必要とせず、パーソナライズや小ロット対応を可能にするこの技術は、単なる印刷手法ではなく、業界のビジネスモデルそのものを再定義する力を持っている。
本シリーズ「印刷の再定義 ── デジタルが変える業界の常識と未来」では、商業印刷、ラベル、軟包装、紙器の4つの主要分野に焦点を当て、それぞれの市場トレンドとデジタル印刷の可能性を深掘りする。
1. 軟包装市場の拡大──都市化・単身化・環境意識が生む新需要
軟包装市場は世界的に拡大を続けている。 その背景には、都市化の進展、単身世帯の増加、そして環境意識の高まりという3つの大きな潮流がある。都市人口の増加と新興国の中間所得層の拡大に伴い、包装された食品・飲料の需要が世界各地で増大している。都市生活者や働く個人は持ち運びやすく衛生的な小包装を求める傾向が強く、軟包装はこのニーズに合致して市場を牽引している。特に北米・欧州では晩婚化や高齢単身者の増加で一人分サイズの即食食品やスナックへの需要が高まり、缶や瓶より軽量で破損しにくい軟包装が選好されている。
また、環境意識の高まりも軟包装市場拡大の重要なドライバーだ。使い捨てプラスチック廃棄への社会的な懸念から、ブランド各社は軽量化・リサイクル可能な包装への切替えを進めている。軟包装は輸送時のCO2排出削減(軽量化効果)やごみ体積の削減といったメリットがあり、多くの企業がサステナブルな包装戦略の一環としてパウチ採用を拡大している。こうした需要要因に応じて、グローバルの軟包装消費量は年間4%前後の成長が続き、2029年には流通数量ベースで約7540億個、市場規模ベースで470億ドル規模に達すると予測されている。※1
2. 消費者ニーズの変化──利便性・安全性・再封機能の進化
消費者の包装に対するニーズは高度化し、多機能化が求められている。 軟包装メーカー各社は利便性・安全性・保存性を高めるための技術革新を加速させている。近年では、再封可能なチャック(ジッパー)や注ぎ口付きキャップを備える製品が急増し、一度開封しても簡単に密閉できることで鮮度保持と使い勝手の両立を図っている。ファスナー式のジッパーはお菓子や冷凍食品など幅広い分野で標準装備となり、近年では「フックtoフック型」のジッパーも登場。粉末や微細な粒子がついていても閉まりやすく、繰り返し開閉に強い仕組みとして注目されている。さらに乳幼児向け製品ではチャイルドレジスタンス(誤開封防止)機能を備えたパウチも開発され、安全性の面でも改良が進んでいる。
利便性と安全性の両立を図る工夫も随所に見られる。たとえば調理ソース類のスタンドパウチではノッチ付き設計によりハサミ不要で開封できるようにしつつ、漏れ防止のためフィルム強度を高める設計が採用されている。軟包装は缶や瓶と違い蓋や容器の破片リスクが無く、安全に扱える点も評価される。
「持ち運びやすく、開けやすく、必要な分だけ使って再封できる」進化型パウチ包装は、現代の消費者ニーズに合致し、軟包装の市場価値を一層高めている。

3. サステナブルパッケージの台頭──モノマテリアルとPCR素材の革新
使用後までを見据えた「サステナブルな包装」への転換が軟包装業界で急速に進んでいる。 特に注目されるのが、モノマテリアル(単一素材)構造へのシフトと、PCR(使用済みプラスチック由来)素材の活用という二つの革新だ。これまで軟包装は、複数素材を組み合わせることで機能性を高めてきたが、その一方で、リサイクルの難しさが課題とされてきた。モノマテリアル化の動きは、こうした課題に対する業界の本質的な解決策であり、素材の単純化によって回収・再利用の効率を高めることを目的としている。
また、PCR素材の活用は、資源循環の観点から重要な取り組みである。使用済みプラスチックを再資源化し、再び包装材として活用することで、廃棄物の削減と原材料の持続可能な利用を両立させることが可能となる。
これらの技術革新は、単なる素材の置き換えにとどまらず、製品ライフサイクル全体を見直す契機となっている。企業は今、環境配慮を競争力の一部と捉え、包装設計においても「循環型社会への貢献」という視点を強く意識するようになってきている。
軟包装はその軽量性や省資源性から、もともと環境適応力の高い形態であるが、今後はさらに「使い終わった後まで責任を持つ」設計思想が求められる。モノマテリアル化とPCR素材の活用は、そうした未来に向けた重要なステップであり、業界全体として持続可能なパッケージの実現に向けた取り組みが加速している。
4. デジタル印刷の技術力──柔軟性・スピード・環境対応の三位一体
軟包装分野におけるデジタル印刷は、柔軟性・俊敏性・環境適応力という三要素を兼ね備えた革新的技術として注目される。 柔軟性の面では、版を必要としないデジタル方式により 小ロット多品種の印刷を効率良くこなせるのが利点だ。ブランド各社は季節限定デザインや地域ごとの言語表示などを頻繁に変更でき、市場のセグメント細分化やSKU増加に機動的に対応している。実際、商品のバリエーション増に合わせてパッケージデザインを次々刷新する戦略が一般化しつつあり、従来のアナログ印刷では対応が難しかったこのニーズをデジタル印刷が支えている。
スピードの面でもデジタル印刷は大きな強みだ。前準備がほぼ不要なため注文から出荷までの時間を劇的に短縮できる。例えば新商品のパッケージを数日以内に市場投入するといった従来不可能だったスピード対応が可能となり、ブランドの迅速な市場投入に直結している。印刷工程の自動化やワークフローのデジタル統合も進んでおり、需要予測に応じて必要な分だけ印刷することで在庫ロスや売切れリスクを最小化するサプライチェーンの実現にも寄与している。

さらに環境対応の観点でも、デジタル印刷は包装印刷の持続可能性を高める技術として評価される。版材料や現像廃液を出さず、印刷時の紙・フィルム廃棄(損紙)も極小で済むため、製造段階のカーボンフットプリント削減に効果的だ。またUV硬化型のような揮発性化学物質を用いないインクシステムではVOC(揮発性有機化合物)の排出が抑制され、食品包装にも安心して使える。つまりデジタル印刷は軟包装分野において「柔軟な対応力」「生産の迅速性」「環境への優しさ」を同時に実現するソリューションであり、これらはまさに2020年代の包装業界に求められるキーワードとなっている。
5. 導入事例から見る未来──グローバルブランドの軟包装戦略
世界のトップブランドも、軟包装への戦略的転換を積極的に進めている。その方向性は、「サステナブル素材への切替え」と「デジタル技術のマーケティング活用」の二軸に集約される。
前者の代表的な取り組みとしては、ジュース飲料を展開する老舗ブランドが、従来のアルミ箔入り多層フィルムから、100%ポリプロピレン製のリサイクル可能なパウチへの切替えを発表した事例がある。年間20億個以上に及ぶ欧州市場の全パウチを対象とした大胆な施策であり、サステナビリティを軸に包装刷新に踏み切った象徴的な動きといえる。
後者の事例としては、スプレッド食品やチョコレート菓子を展開する世界的ブランドが、デジタル印刷技術を活用したユニークラベルキャンペーンを実施している。数百万種類の異なるデザインを製造することで話題を呼び、消費者とのエンゲージメント強化に成功している。また、季節限定商品に地域ごとの絵柄を施すことで、バージョン違い商品の迅速な市場投入を可能にしている。
これらグローバルブランドの事例からは、軟包装の未来像として「環境配慮素材への大胆なシフト」と「デジタル技術による消費者エンゲージメント向上」が浮かび上がる。すなわち、持続可能性とマーケティング効果の双方を追求する軟包装戦略が今後の世界標準になっていくと考えられる。
6. HP Indigoデジタル印刷テクノロジー──軟包装印刷の課題を解決する技術と知見
HP Indigoはデジタル印刷のパイオニアとして、軟包装印刷における様々な課題解決に寄与する製品・技術、そして知見を提供している。
HP Indigoの液体電子写真(LEP)方式は微細な液体トナーを用いる独自技術で、最大7色の高精細印刷によりグラビア印刷に匹敵する発色と網点再現性を実現する。これにより食品・日用品大手を含む多くのブランドが、ラベルやパウチに求める鮮やかなブランドカラーをデジタルでも忠実に再現できるようになった。また、HP Indigoデジタル印刷機は一度のセットアップで複数デザインを連続印刷できるため、多品種化するパッケージ需要にもワンストップで応えられる。版の作成やインキ交換の手間が無いためロスが極小化し、生産計画の自由度も飛躍的に高まっている。
加えて、食品包装対応インクと工程ソリューションもHP Indigoの強みだ。使用するエレクトロインキは、適切なバリア層と組み合わせれば食品パッケージにも安全に利用可能である。実際、Indigo印刷物用の接着剤・コーティングは主要な食品安全基準に適合しており、食品包装のデジタル印刷化を阻むインク由来の障壁をクリアしている。また印刷工程で有機溶剤を使わないため工場内のVOC排出もゼロに近く、環境面・衛生面で安心できる点も特徴だ。

さらにHPが提供するPack Readyラミネーションは、Indigoで印刷した軟包装フィルムを即座にラミネート加工して耐水・耐熱性を付与できる画期的なソリューションだ。従来は接着剤の乾燥に数日かかっていたパウチ加工をわずか数時間で完了でき、生産リードタイムを圧縮するとともに溶剤系接着剤を不要にすることで環境負荷も低減する。
このような統合的技術基盤に支えられ、世界各地でデジタル印刷専門の軟包装サービスも次々に誕生している。米国発のePac社はHP Indigoを各国に数十台規模で導入し、小ロット高速提供に特化したパウチ印刷ビジネスモデルで成功を収めている。
総じてHP Indigoのテクノロジーと長年の応用知見は、軟包装印刷における品質・生産性・安全性の課題を高水準で解決しうるプラットフォームとなっており、デジタル時代の新標準として業界をリードしている。
まとめと提言
軟包装印刷の未来は、進化する消費者ニーズとサステナビリティへの要請に応じて、大きく再定義されつつある。都市化や単身世帯の増加に伴い、利便性と携帯性を兼ね備えた小容量パウチの需要は今後も拡大が見込まれる。一方で、環境負荷の低減という社会的責任に応えるべく、素材面ではモノマテリアル化や再生材の活用といった技術革新が進み、プロセス面では高速自動化ラインやスマートリフィルなど、循環型モデルへの転換が模索されている。
加えて、デジタル印刷技術の進展は軟包装の価値を拡張し、パーソナライゼーションや需給マッチングの精度向上を通じて、マーケティング効果とロス削減の両立を可能にしている。
こうした変革期において、軟包装に関わる各企業に対し、以下の3点を提言したい。
1. サステナブル設計の徹底
単一素材化や再生プラスチックの積極的な採用を通じて、規制に先んじた循環型パッケージ設計を推進することが望ましい。これは環境対応にとどまらず、企業の中長期的なブランド価値向上に資する戦略的投資と位置付けられる。
2. 最新技術への対応
高速充填機やデジタル印刷設備へのアップグレードを検討し、需要の細分化や短納期化に対応可能な柔軟な生産体制の構築が求められる。特にデジタル印刷は、在庫削減と市場対応力の強化において有効な手段となり得る。
3. 付加価値機能の追求
消費者視点に立ち、利便性と再利用性を兼ね備えたパッケージ機能の開発を進めることが重要である。再封ジッパーや計量可能なディスペンサー機構、スマートタグなどの導入により、体験価値の高い包装を提供することが、他社との差別化につながる。
軟包装は今後も世界的な成長が見込まれる分野であり、その持続的発展には、環境と調和し、消費者に支持されるイノベーションの継続が不可欠である。本稿で述べた技術・素材・デザインの革新は、あくまで一例に過ぎないが、こうした取り組みを積極的に取り入れることで、軟包装印刷は「消費者ニーズとサステナビリティに応える」次のステージへと着実に進化していくものと考えられる。

- 永嶋 ゆり
- 株式会社 日本HP
- インダストリアルセールス本部 マーケティング部
- シニアスペシャリスト
2011年に日本ヒューレット・パッカード(現:日本HP)に入社以来、デジタル印刷機のマーケティングを中心に、印刷業界の多岐にわたる分野で豊富な経験を積んでまいりました。
グローバル市場の動向を的確に捉える分析力と、営業・マーケティング・市場開拓の実務経験を融合させ、業界内外への情報発信を通じて、顧客企業の成長支援および印刷産業の価値向上に尽力しています。
出典
- ※1 Smithers/The Future of Digital Print for Packaging to 2030