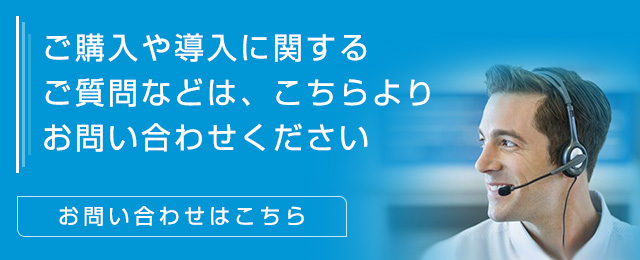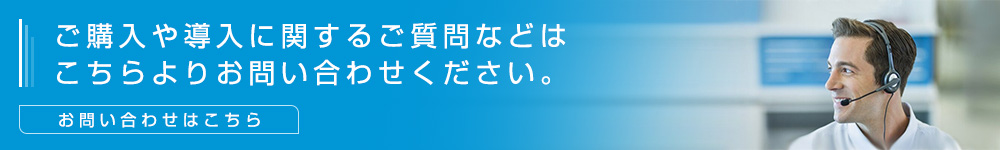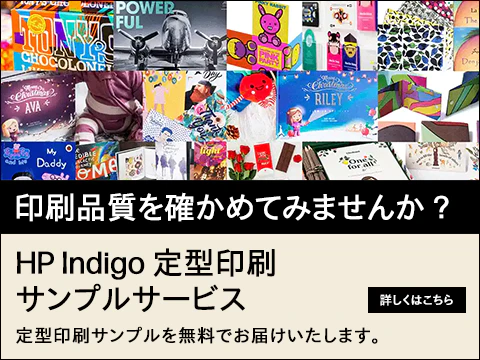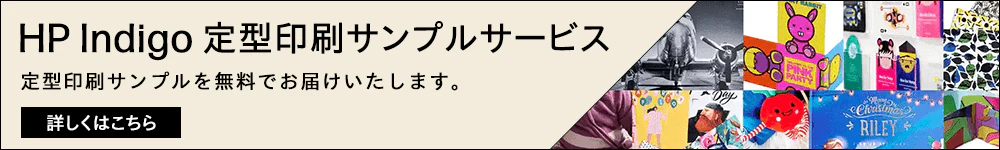ラベル印刷の再定義
──── スピード・柔軟性・環境対応を実現するデジタルの力
印刷の再定義 ── デジタルが変える業界の常識と未来
印刷業界は今、かつてない構造変化と技術革新の真っただ中にある。
大量生産・低価格競争という旧来の常識はすでに限界を迎え、求められるのは「柔軟性」「付加価値」「環境対応」といった新たな競争軸である。
その中心にあるのが、デジタル印刷という選択肢だ。
版を必要とせず、パーソナライズや小ロット対応を可能にするこの技術は、単なる印刷手法ではなく、業界のビジネスモデルそのものを再定義する力を持っている。
本シリーズ「印刷の再定義 ── デジタルが変える業界の常識と未来」では、商業印刷、ラベル、軟包装、紙器の4つの主要分野に焦点を当て、それぞれの市場トレンドとデジタル印刷の可能性を深掘りする。
1. ラベル市場の進化──用途多様化と高付加価値化の波
ラベル印刷市場は従来の大量生産から、多品種・高付加価値志向へと進化している。世界のラベル印刷市場規模は2024年時点で約450億ドル(約5兆円)に達し、年平均4%前後で成長を続けている※1。その用途は食品・飲料、日用品、医薬品、物流など極めて広範囲であり、企業は商品カテゴリー毎に異なるラベルニーズに対応してきた。
近年、特に用途の多様化が顕著であり、ラベルは単なる製品表示を超えて、ブランド価値や機能性を付与する重要なメディアとして位置づけられている。高級化粧品やプレミアム飲料などの分野では、浮き出し加工や箔押し、独創的な形状など、視覚・触覚に訴求するラベルが求められており、ラベル自体がブランド体験の一部を構成するようになっている。
また、機能性ラベルの需要も拡大している。物流や医療分野では、QRコードやバーコード、RFIDタグを組み込んだラベルが普及し、トラッキングや真贋判定などの高度な機能を担っている。消費財分野においても、プロモーションやキャンペーン用途として、可変データ印刷による一枚ごとに異なるデザイン・メッセージを施したラベルが活用されており、消費者参加型のマーケティング施策が展開されている。

さらに、SKU(品目)の増加に伴う小ロット・多品種化も市場構造に変革をもたらしている。1970年代に約3万種であった米国スーパーマーケットの平均商品数は、現在では12万種を超えるとも言われている※2。食品・日用品メーカー各社は、風味や容量の違いによるバリエーションを次々と市場投入しており、それぞれに対応したラベルの準備が求められている。その結果、印刷ロットは小さく分散し、従来のような大量一括印刷では対応が困難となり、ニーズに応じた頻繁な印刷が必要とされる状況が生まれている。
このような市場環境の変化に伴い、ラベル印刷会社は従来型の生産体制から、より柔軟かつ高効率な印刷プロセスへの転換を迫られている。生産計画はよりダイナミックなものとなり、短納期・多品種対応を前提とした設備投資やワークフローの再構築が不可欠となっている。
要約すれば、ラベル市場は「一種類を大量に」から「多種類を適量ずつ」へシフトし、その中でラベル自体の質的価値も向上している。多様な用途で付加価値を発揮するラベルへの期待が高まり、これに応える印刷技術・プロセスの革新が不可欠となっている。
2. 成長分野を読み解く──飲料・日用品・物流の最新動向
食品・飲料、日用品、物流は、ラベル印刷市場における主要な成長分野であり、それぞれ固有のトレンドが業界全体の進化を牽引している。
飲料分野:最大セグメントとしての多様化と環境対応
飲料分野では、ビールやソフトドリンク、清涼飲料水、アルコール飲料など、幅広い製品群がラベル需要を創出している。飲料用ラベルは世界のラベル印刷需要の約半分を占める最大セグメントであり、2024年時点では全ラベル印刷面積の約52%を占めるとの報告もある※1。

炭酸飲料やペットボトル飲料では、フィルム系ラベルやシュリンクスリーブが主流であるが、近年はデザイン性に加え、環境対応への要求が高まっている。たとえば日本や韓国では、ペットボトルのリサイクル効率向上を目的とした「ラベルレスボトル」の取り組みが拡大しており、大手飲料メーカーはボトル本体への直接印字や最小限のバンドラベルによる情報提供を進めている。これに伴い、ラベル印刷業界は新たな技術開発への対応を迫られている。
一方で、クラフトビールや地域限定飲料など、少量多品種の市場が世界的に拡大したことも、ラベル印刷に革新をもたらしている。これらの製品では、凝った意匠や物語性を持つラベルによって差別化を図るケースが多く、デジタル印刷技術を活用した限定版ラベルの展開が増加している。欧米のクラフトビール醸造所では、季節ごとに異なるデザインのラベルを少量印刷し、消費者のコレクション欲求を刺激するマーケティングが成功している。また、飲料大手もスポーツ大会や映画とのコラボレーションによる期間限定ラベルを展開するなど、多様なニーズに対応可能なラベル供給体制の構築が求められている。
日用品分野:ブランド演出と規制対応の両立
日用品分野において、シャンプー、洗剤、化粧品などのラベルは、ブランドイメージ形成に直結する重要な要素である。高級志向の化粧品では、前述の通り、浮き出し加工や箔押しなどを施した高意匠ラベルが好まれる傾向にある。一方、日常消費財では、ミニマルかつ環境配慮型のラベルが台頭しており、欧州ではケミカルフリーやオーガニックコスメの増加に伴い、未晒し紙ラベルや生分解性素材の採用が進んでいる。
加えて、各国で成分表示やリサイクル表示の義務化が強化されていることから、表示情報量の増加に対応する必要が生じている。特に小型容器では、ピールオフ式の多層ラベルや冊子ラベルの採用が進んでおり、限られたスペースでの情報提供とブランド演出の両立が求められている。日用品メーカー各社は、こうした規制対応とマーケティング施策を両立すべく、ラベルデザインおよび印刷方式の最適化に取り組んでいる。
物流分野:大量・即時対応と持続可能性への適応
物流分野におけるラベル需要は、ネット通販やオンデマンド配送の拡大に伴い、急速に増加している。出荷ラベルや荷札ラベルの発行枚数は爆発的に伸びており、特に宅配便の増加により、宛名やバーコードを印刷した感熱ラベルの消費量が急増している。
物流現場では、印刷と貼付の自動化が進んでおり、従来は人手で行っていたラベル貼付作業が高速ライン化されている。一般的にはロール状のラベルから台紙を剥離して貼付する方式が採用されているが、近年ではライナーレスラベル(台紙を持たない粘着ラベル)の導入も進みつつある。ライナーレスラベルは剥離紙の廃棄が不要で環境負荷が低いため、欧米の大手物流企業が採用を検討しており、印刷会社も感熱紙や粘着剤の改良を通じて高信頼性の製品開発を進めている。
さらに、トレーサビリティ強化の流れもラベル需要を押し上げている。国際貿易や食品流通では、各商品にユニークIDを割り振り、QRコード化する動きが加速しており、物流ラベルに高密度コードを印刷するニーズが拡大している。これに対応するためには、高解像度のデジタル印刷機による微細コードの鮮明な印字が不可欠である。
加えて、欧州連合が導入を予定している「DPP(Digital Product Passport:デジタル製品パスポート)」では、製品ごとの環境情報や成分情報をデータベースに紐付け、2次元コードで表示する仕組みが検討されている※1。この制度が実現すれば、あらゆる製品に追加のQRラベルが必要となり、ラベル印刷業界に新たな需要と技術要件をもたらすことは確実である。
以上の通り、飲料・日用品・物流の各分野において、ラベル需要の質的・量的変化が顕著である。飲料分野では、デザイン性と環境対応の両立が課題となり、日用品分野では情報量の増加とブランド演出の融合が求められている。物流分野では、大量かつ即時対応可能な印刷体制と、自動化・持続可能性への適応が競争力の鍵を握る。
これらの最新動向を的確に捉え、柔軟かつ高品質な印刷ソリューションを提供できるか否かが、ラベル印刷企業の市場競争力を左右する重要な要因となっている。

3. 印刷方式の変革──デジタル化がもたらす生産性革命
デジタル印刷の進展は、ラベル印刷の生産性に根本的な変化をもたらしている。従来主流であったオフセットやフレキソなどのアナログ印刷方式は、大量生産において高品質・低コストを実現する一方で、版の作成や色調整、段取り替えに時間と手間を要し、小ロットや短納期への対応には限界があった。その結果、「アナログファースト」の発想が業界に定着していた。
しかし、過去20年で導入が進んだデジタル印刷機、特にHP Indigoに代表される液体トナー方式の台頭により、この常識は大きく変わり始めている。2025年時点で、ラベル印刷におけるデジタル印刷の数量ベースのシェアは約7%に留まるが、金額ベースでは23%超に達しており、短納期・小ロット用途を中心に存在感を高めている※3。
最新世代のデジタル印刷機は、印刷速度や対応幅が飛躍的に向上し、中〜長尺ジョブでもアナログ印刷に匹敵する生産性を発揮している。HP Indigo V12は分速最大120メートルの高速印刷を実現し、従来フレキソ印刷でしか対応できなかった領域にも対応可能となった。これにより、アナログとデジタルの生産量の境界は曖昧になり、「まずデジタル、必要に応じてアナログ」という運用が現実味を帯びてきた。
デジタル印刷の最大の利点は、段取り時間と廃棄ロスの大幅な削減にある。版の製版・交換が不要なためジョブ切替えが迅速で、印刷開始直後から高い歩留まりが得られる。印刷前のテストや色合わせに伴う損紙も削減できるため、資材コストの低減と生産効率の向上に直結している。
また、労働生産性の向上も顕著である。アナログ印刷では熟練オペレーターの技術が不可欠だったが、デジタル印刷機は高度な自動制御と検査機能を備え、常に安定した発色と見当精度を維持する。HP Indigoでは内蔵カメラが色ズレや濃度をリアルタイムで補正し、オフセット印刷に匹敵する品質を自動で再現する。これにより、1人のオペレーターが複数台を管理する運用も可能となっている。
さらに、デジタル印刷と周辺工程の自動化統合も進展している。クラウドベースの生産管理システムHP PrintOSと連携することで、受注から印刷指示、仕上げ加工、出荷までのプロセスを一元管理する企業が増加している。欧州では、HP Indigoデジタル印刷機と後工程を直結させた「デジタルファクトリー」が稼働しており、バーコードによるジョブ情報の引き継ぎにより、印刷からラミネート・カッティング・梱包までを自動化。人手不足への対応と生産性向上を両立し、夜間の無人運転も視野に入っている。
もっとも、現時点ではデジタル印刷の数量シェアは限定的であり、アナログ印刷とのハイブリッド運用が現実的な選択肢となるケースも多い。多くの印刷会社では、メインのアナログ印刷機で安定稼働させつつ、小ロットはデジタル機に振り分けることで両者の利点を最大化している。
ただし、デジタル印刷機の高速・大型化が進めば、こうした棲み分けも変化する可能性が高い。アナログ印刷機においても自動化・省力化を強化しており、インク調合の自動化、段取り時間短縮のための自動版交換など、対策が講じられている。言い換えれば、印刷工程全体のデジタル化・自動化が、ラベル業界の生産性を底上げする方向へと進展していると言える。

4. 環境対応ラベルの最前線──素材革新とラベルレス化の潮流
サステナビリティへの関心の高まりは、ラベル印刷業界にも革新を促している。企業は製品の環境負荷低減を求められ、ラベルにおいても素材選定や設計思想に変化が生じている。
まず注目すべきは、ラベル素材の進化である。従来のフィルムやコート紙に代わり、再生材や生分解性素材の採用が進み、ライナー紙の回収・再利用を含む循環型モデルも構築されつつある。接着剤においても、リサイクル工程を妨げない処方開発が進展しており、素材選定は環境適合性を軸に再定義されている。
次に、ラベルレス化の動きが加速している。特にペットボトルなどのプラスチック容器では、ラベルを省略することで分別の手間を減らし、リサイクル効率を高める試みが広がっている。ボトル本体への直接印字や、最小限の情報表示によるパッケージ設計が進み、消費者からも好意的に受け止められている。
加えて、ライナーレスラベルの普及も進行中である。剥離紙を持たない粘着ラベルは廃棄物削減に寄与し、物流用途を中心に採用が拡大している。技術的課題は残るものの、専用機器やコーティング技術の進化により実用化が進んでいる。
さらに、容器との同材質ラベルや水洗除去可能な接着剤の採用など、リサイクル容易性を高める設計も注目される。欧州では製品設計段階での環境適合性が求められる動きもあり、グローバルブランドはラベル仕様の見直しを迫られている。
印刷方式においても、デジタル印刷は環境対応の観点から優位性を示している。版や薬品を使用せず、必要な分だけ印刷するオンデマンド生産により、廃棄物やCO₂排出の削減に貢献している。
このように、環境対応ラベルは素材・設計・印刷方式の各側面で進化している。ただし、環境配慮と実用性のバランスを取ることが重要であり、印刷会社には顧客のサステナビリティ戦略に寄り添った提案力が求められている。市場の変化を捉え、柔軟かつ創造的なソリューションを提供できるかが、今後の競争力を左右するだろう。
5. ハイブリッド印刷の台頭──効率と表現力を両立する選択肢
デジタルとアナログの長所を融合したハイブリッド印刷が、ラベル印刷の新たな選択肢として注目を集めている。高い表現力と柔軟な生産性を両立できる点が評価され、特に多品種・小ロット対応が求められる業界において導入が進んでいる。
徳島県鳴門市に本社を構える釣り糸メーカー、ワイ・ジー・ケーはその代表的な事例である。同社は自社ブランド「XBRAID」の立ち上げに伴い、パッケージ戦略とラベル運用の両面で革新を図った。従来のラベル管理では、数百〜千種類に及ぶ品番ごとの在庫管理が課題となっていたが、HP Indigoによるデジタル印刷の採用により、版代不要・可変印刷対応・小ロット発注が可能となり、在庫圧縮と業務効率化を実現した。
さらに、印字と貼付を同時に行う「プリンターラベラー」を導入することで、ラベルの最終工程までを一貫して自動化。これにより、従来は手作業で対応していた小ロット品種のラベル貼付も効率的に処理できるようになった。同社では、ラベルの可変情報(長さ・太さ・強度)をブランドフォントで統一し、製品の世界観を損なうことなく運用している。
このようなハイブリッド運用は、単なる生産効率の向上にとどまらず、ブランド価値の訴求や環境対応にも寄与している。ワイ・ジー・ケーではFSC認証紙の採用や剥離紙の再資源化など、サステナブルな取り組みも並行して進めており、印刷方式の選択が企業姿勢の表現手段となっている点も示唆的である。
総じて、ハイブリッド印刷は「いいとこ取り」の次世代プラットフォームとして期待されている。ラベルの高付加価値化と多様化に応えるため、効率と品質を両立できるハイブリッドソリューションは今後ますます存在感を増すだろう。印刷会社にとっては初期投資の判断が悩ましいが、競合との差別化や生産体制の柔軟性確保という観点から、戦略的導入を検討する価値は十分にある。
6. デジタル印刷の導入効果──小ロット・高意匠・短納期を実現
ラベル印刷におけるデジタル技術の導入は、小ロット対応力の向上、高度な意匠表現、そしてリードタイム短縮といった形で明確な成果をもたらしている。印刷会社やブランドオーナーがデジタル印刷を採用する主な理由は、次の3点に集約される。
第一に、小ロット生産の効率化と採算性の向上である。従来は版代や段取りコストの負担が大きく、極小ロット案件は採算が合わないケースも多かった。デジタル印刷では版が不要なため、経済ロットの下限が大幅に下がり、これまで敬遠されていた案件も積極的に受注可能となった。結果として、新規顧客の獲得や小口案件の収益化が進み、ビジネス機会の拡大につながっている。
第二に、可変データ印刷によるパーソナライズや多言語対応など、高度な意匠表現が容易である点が挙げられる。シリアル番号や限定デザインの展開はブランド価値の向上に寄与し、グローバル製品においても、国・地域ごとの表示差異に柔軟に対応できる。

第三に、リードタイムの大幅な短縮である。製版やインキ調色が不要なうえ、修正もデータ上で即時対応できるため、デザイン確定から量産までの時間が圧縮される。特にトレンド商品やシーズナル商品では、市場投入のスピードが競争力に直結する。
このスピードはサプライチェーン全体にも波及する。需要変動の大きい製品では、必要な時に必要な量だけ印刷できるため、在庫リスクや廃棄ロスを抑制できる。
以上、デジタル印刷導入の効果を総括すれば、「小ロットは損」と言われた常識が覆り、多品種少量でも利益を生む生産体制を構築できる点が最も大きい。加えて、これまでは不可能だったきめ細かなマーケティング表現をラベル上で実現し、商品付加価値を高められることも見逃せない。そして何より、迅速な市場対応力は不確実性の高い時代において事業リスクを低減する武器となる。デジタル印刷の導入は単なる印刷工程の変更にとどまらず、ビジネスモデルそのものを最適化する可能性を秘めていると言えよう。
7. HP Indigoデジタル印刷テクノロジー──ラベル印刷の未来を支える技術とノウハウ
HPは、Indigoデジタル印刷機を中核に、ラベル印刷の未来を支える包括的な製品・技術・ノウハウを提供している。その強みは、ハードウェアにとどまらず、ソフトウェア、サービス、人材育成を含むエコシステム型の支援体制にある。単なる機械販売ではなく、ユーザーと伴走しながら成果を創出する姿勢が特徴であり、複雑化するラベル印刷ビジネスにおいて、機械性能以上に重要な「活かし方」を支えている。この包括的アプローチこそが、HP Indigoが世界中で選ばれ続ける理由の一つだと考えている。
まとめと提言
ラベル印刷業界は、用途の多様化と高付加価値化、そしてデジタル技術の進展により、大きな転換期を迎えている。飲料・日用品・物流などの成長分野では、デザイン性・情報量・スピードへの対応力が求められ、印刷会社には柔軟かつ俊敏な体制が不可欠となっている。
デジタル印刷は、小ロットの採算性向上、パーソナライズ対応、リードタイム短縮など、具体的な成果をもたらしており、サプライチェーン全体の最適化にも貢献している。また、必要な分だけを生産するオンデマンド型の運用は、環境負荷の低減と経済合理性を両立する持続可能な手法として注目されている。
今後のラベル印刷は、「スピード・柔軟性・環境対応」を備えたデジタル駆動型生産へと進化していく。その実現には、印刷機だけでなく、ノウハウとサポートを含めた総合力が不可欠である。HPは、こうした総合力でラベル印刷会社の皆様の成長を支援している。
デジタル技術と持続可能なイノベーションを積極的に取り入れることで、ラベル印刷業界は市場の要求に応えつつ、持続的な成長を実現できる。本稿が、皆様の戦略策定の一助となれば幸いである。

- 永嶋 ゆり
- 株式会社 日本HP
- インダストリアルセールス本部 マーケティング部
- シニアスペシャリスト
2011年に日本ヒューレット・パッカード(現:日本HP)に入社以来、デジタル印刷機のマーケティングを中心に、印刷業界の多岐にわたる分野で豊富な経験を積んでまいりました。
グローバル市場の動向を的確に捉える分析力と、営業・マーケティング・市場開拓の実務経験を融合させ、業界内外への情報発信を通じて、顧客企業の成長支援および印刷産業の価値向上に尽力しています。
出典
- ※1 Smithers/The Future of Printed Labels to 2029
- ※2 US food industry association
- ※3 Smithers/The Future of Digital Print for Packaging to 2030