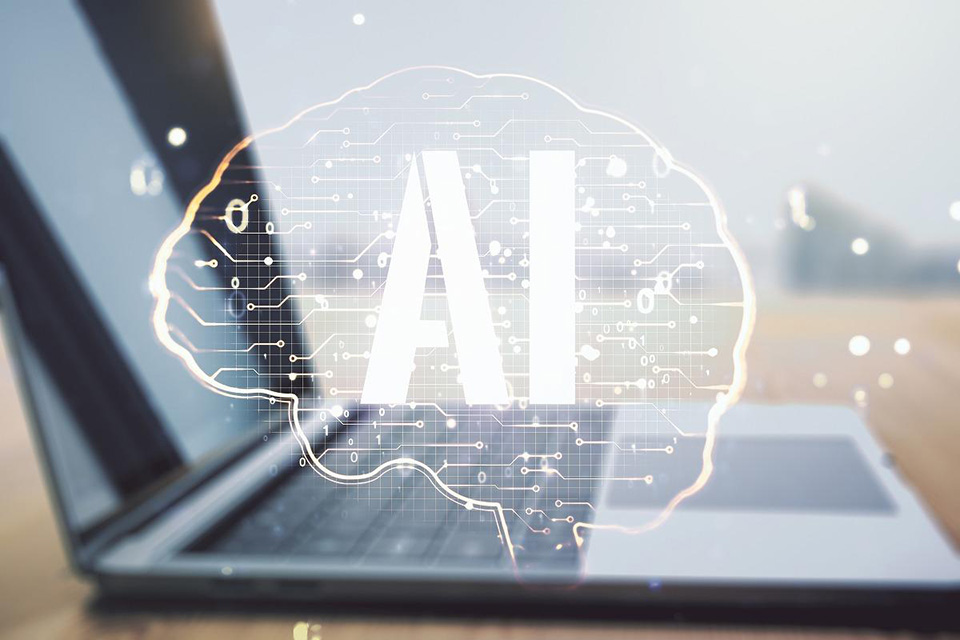AI搭載PCは本当に“設計業務向き”か? プロが語る選定ポイント
2025-08-28

製造業におけるDX進展が加速し、Windows 10のサポート終了なども相まって、3次元CADやCAE(コンピューター支援エンジニアリング)などの領域で、高負荷業務に対応可能な性能を備えたPCが注目を浴びている。しかし、AI処理に特化したNPU(Neural Processing Unit)を搭載した「AI PC」を導入すればOKかといえばそうではない。周辺業務も含めた業務全体を長時間、快適に稼働可能な「数年先」を見据えたインフラ基盤を整備する必要がある。本記事では、設計業務に最適な次世代ワークステーション選定のポイントを解説する。
転載元:SeizoTrend
2025年7月29日掲載記事より転載
本記事は ビジネス+ITより許諾を得て掲載しています。
Windows 10のサポート終了で高まる「業務インフラ」再構築
2025年10月14日、Windows 10のサポートが終了する。サポート終了により、直ちにWindows 10搭載のPCが使用不能になるわけではないが、セキュリティ更新が停止すると、業務用端末としての運用にはリスクが生じるため、設計や解析といった業務を日常的に行う製造業において、早急な対応が求められている。
同時に、設計業務の在り方自体も変化しつつある。インテルの最新プロセッサーを搭載した「AI PC」と呼ばれる新たなカテゴリーのPCが登場し、Windows 11では「Microsoft Copilot」をはじめとする生成AI機能が標準搭載されるようになった。これにより、従来の3D CADやCAEといったエンジニアリング業務に、生成AIの支援を組み込む動きが加速している。
もちろん、現時点でAIが設計や解析作業の中核を担っているわけではない。しかし、設計レビュー資料の草案づくりや報告書の下書きといった周辺業務をAIに任せることで、エンジニアが本来の業務に集中できる環境が整いつつある。こうした変化を追い風に変えるためには、業務を支えるIT基盤の整備が、今後ますます重要になっていくといえるだろう。
以下で、設計業務の現場が抱える課題と対策について詳しくみていこう。
「今の業務に合ったワークステーション環境」をどう作る?
製造業、とりわけ設計や解析を担う現場では、「PCやワークステーションのスペックが足りていないのでは」という悩みが絶えない。
こうした課題について、日本HPエンタープライズ営業統括ソリューション営業本部ワークステーション営業部市場開発担当部長の川口剛史氏は「3D CADやCAE、さらにはレンダリングなどの高負荷作業を円滑に進めるためには、CPUやGPUだけでなく、メモリやストレージの性能も不可欠です」と話す。
もちろん、現時点でAIが設計や解析作業の中核を担っているわけではない。しかし、設計レビュー資料の草案づくりや報告書の下書きといった周辺業務をAIに任せることで、エンジニアが本来の業務に集中できる環境が整いつつある。こうした変化を追い風に変えるためには、業務を支えるIT基盤の整備が、今後ますます重要になっていくといえるだろう。
ソフトウェアが年々高機能化する一方で、ハードウェアの性能が起因でそれを生かしきれないという声は少なくないということだ。
エンタープライズ営業統括
ソリューション営業本部ワークステーション営業部市場開発担当部長
川口剛史氏
「Windows 11への移行のタイミングで、現場のお客さまからは、日々使っているワークステーションの構成が今の業務に合っているのかというご相談を多くいただきます」(川口氏)
実際に、Windows 11への移行に際しては、既存PCとの互換性やドライバー対応が課題となる。また、3D CAD• CAEのような高負荷業務では、一般的なノートPCでは性能的に不足する点が課題となっている。また、近年注目されているのが、NPUを搭載したAI PCである。Al処理をCPUからNPUにオフロードすることで、CADやCAEなどの業務中でもPCのパフォーマンスが落ちにくく、作業効率が維持される。
一方で、ハードウェアの更新が必要だからといって、単純にPCを買い替えれば済むという単純な話ではない。CADやCAEの業務では、使用ソフトの互換性や、周辺機器との動作検証、ドライパーの整合性など、環境全体の最適化が欠かせない。
特にWindows 11への移行に際しては、過去にWindows 7から10への移行で苦労した経験がある企業も多く、慎重な対応が求められている。
「Windows 11への移行には、業務に最適化されたアセスメントが必要です。ただの置き換えではなく、エンジニアの生産性を維持・向上させるために、業務フロー全体を見据えた移行計画が重要です。日本HPでは、3次元CADならアセンブリーの規模や使用頻度、CAEなら解析の種類や所要時間など、具体的な使用状況をヒアリングしたうえで、最適な構成をご提案しています」(川口氏)
川口氏は、「必要に応じてBIOS設定の変更や、HP独自のパフォーマンスツールを用いたボトルネックの可視化といった対応も行っている」と語った。では、高負荷業務を支えるIT基盤として求められるポイントとはどのようなものだろうか。
設計業務に最適な構成を実現するHPのワークステーション
高負荷業務を支えるIT基盤として、今後求められるのは「CPUやGPUの性能だけに偏らない、バランスの取れた構成」である。
特にWindows 11移行後を見据えるなら、性能面ではCADやCAEといった設計・解析業務に加えて、CopilotなどAlツールの同時利用にも耐える、マルチタスク性能やストレージ高速化などが重視される。NPU (Al処理専用ユニット)を備えたプロセッサーの登場も、今後のインフラ設計に大きく影響を与えるポイントだといえる。
川口氏は、こうした要件を満たす製品群として、HPの最新ワークステーションのラインナップを紹介した。いずれも3D CADやCAEなど製品の設計や開発のツールを稼働させる高性能・高信頼性のワークステーション製品群となっている。
まず、デスクトップワークステーション「zシリーズ」には以下の2機種がある。
1つ目の「Z2 Tower G1i」は、インテル Core Ultra プロセッサー(シリーズ2)(開発コードネーム:Arrow Lake-S)のウルトラナインKプロセッサーを搭載可能だ。
「Al処理に適したNPUも内蔵しており、従来機にはなかったAI PCとしてのポテンシャルを備えています。最大256GBのメモリを搭載可能で、NVIDIA RTX 6000 Ada/Blackwellなど最新GPUにも対応し、CADやCAEで求められる処理性能を十分に発揮できます」(川口氏)
2つ目の「Z2 SFF(スモール・フォーム・ファクタ) Gli」は、従来よりも筐体サイズを20%削減した省スペースモデルでありながら、タワー型と同様のCPUを搭載可能だ。
「グラフィックにはNVIDIAのRTX 4000 SFF Adaというグラフィックカードを搭載可能ですので、非常にコンパクトながらも、ワークステーションとして性能面では申し分ない製品です」(川口氏)
「Al処理に適したNPUも内蔵しており、従来機にはなかったAI PCとしてのポテンシャルを備えています。最大256GBのメモリを搭載可能で、NVIDIA RTX 6000 Ada/Blackwellなど最新GPUにも対応し、CADやCAEで求められる処理性能を十分に発揮できます」(川口氏)
3つ目は、場所を選ばず高性能を実現するモパイルワークステーションとして「ZBook X G1i 16インチ」が挙げられる。 「ZBook X」は、メインストリーム製品として、従来モデルと比べてCPU・GPU性能が大幅に向上している。
「内部には2基のファンとベイパーチャンパーを備え、長時間作業でも熱がこもらない冷却設計を採用しています。さらに、TPMや指紋・顔認証といった多屑的なセキュリティ機能も標準搭載し、紛失や盗難時のリモートロック、データ消去にも対応しているため、場所を問わずに安全に3D CADを処理できる製品ということができます」(川口氏)
このように、HPのZワークステーションは、単なる高性能マシンではなく、設計現場のリアルな課題に応える“業務インフラ”としての完成度を備えている。
高性能なCPU・GPUを長時間安定利用できる優位性
川口氏は「Z2シリーズをはじめとするHPのZワークステーションは、Windows 11以降の業務環境を見据えたシステム更新に最適な選択肢です」と話す。
最新のインテル Core Ultra プロセッサーを搭載し、CADツールをより高速かつ安定した環境で稼働させることで、設計業務全体の生産性向上に寄与する。また、専用設計により優れた排熱機構を備えており、高性能なCPUやGPUを長時間にわたり安定して使用できる点が低位性だ。
とりわけZ2 Towerは、従来モデルと比べて筐体を大型化。最大1kWの電源ユニットを搭載可能とすることで、これまでZ2シリーズでは難しかったTDP(熱設計電力)の高いハイエンドGPUの搭載を実現した。これにより、3ワイドサイズのGeForceグラフィックスも扱えるようになり、設計現場におけるワークステーションの選択肢がさらに広がっている。
一方、Z2 SFFは省スペース性と性能のパランスに優れ、限られたデスクスペースでも3D CADの標準機として十分なパフォーマンスを発揮する。モバイルでは、18インチ画面を備えたZBookシリーズが加わり、ハイエンドなデスクトップ環境をそのまま持ち運ぶことも可能になった。
また、NPUを活用することで、AI PCならではの恩恵も期待できる。たとえば、Web会議アプリで背景をぽかす処理をNPUにオフロードすることで、CPU負荷を抑え、全体のパフォーマンスを維持できる。
また、CAD作業中にウイルススキャンが走るといった従来の“業務中断リスク”も、NPUによる裏処理で回避できる可能性が高まっている。さらには、ローカル環境でのAl処理であれば情報漏えいのリスクを低減することも可能だ。
「今後、Alを活用した業務は確実に増えていきます。設計・解析業務における新たな選択肢として、AI PCの活用はさらに加速していく時代にこそ、NPUを搭載した最新のプロセッサーによる快適な業務環境が、エンジニアの生産性を左右します。Windows 11への移行とあわせて、次の世代の業務を支える基盤として、ぜひHPのワークステーションをご検討いただきたいです」(川口氏)
ハードウェアの刷新は、単なる機材更新ではない。Al時代を見据えた、業務インフラの最適化である― 、HPの提案は、その一歩先を見据えたものといえそうだ。
HPは、ビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。
Windows 11 は、AIを活用するための理想的なプラットフォームを提供し、作業の迅速化や創造性の向上をサポートします。ユーザーは、 Windows 11 のCopilotや様々な機能を活用することで、アプリケーションやドキュメントを横断してワークフローを効率化し、生産性を高めることができます。
組織において Windows 11 を導入することで、セキュリティが強化され、生産性とコラボレーションが向上し、より直感的でパーソナライズされた体験が可能になります。セキュリティインシデントの削減、ワークフローとコラボレーションの加速、セキュリティチームとITチームの生産性向上などが期待できる Windows 11 へのアップグレードは、長期的に経済的な選択です。旧 Windows OSをご利用の場合は、AIの力を活用しビジネスをさらに前進させるために、Windows 11 の導入をご検討ください。
※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。


ハイブリッドワークに最適化された、Windows 11 Pro+HP ビジネスPC
ハイブリッドなワークプレイス向けに設計された Windows 11 Pro は、さらに効率的、シームレス、安全に働くために必要なビジネス機能と管理機能があります。HPのビジネスPCに搭載しているHP独自機能は Windows 11 で強化された機能を補完し、利便性と生産性を高めます。
詳細はこちら