HP Tech&Decive TV 以外のコンテンツも検索対象となります。

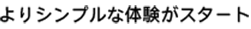
2022.08.08
「サステナベーション」の視点から考える日本企業の未来像
事業価値の再発見は「課題基点の発想」から
若手のみならず、ミドル層以上の意識も変わり始めた
―― サステナビリティに対する考え方・捉え方は世代により大きな違いがあると思います。企業はその違いをどう認識し、自社の経営方針に反映すべきでしょうか。
藤原氏 ミレニアル世代やZ世代は、サステナビリティに対する感度が非常に高いといわれていますが、若手メンバーと話していると、本気でそう考えているのだと、ひしひしと感じます。
若い世代の方々は、自分が取り組んでいる仕事に対して、「社会的な意義があるかどうか」「将来的に社会課題の解決につながるのかどうか」を強く意識し、そうではない仕事を続けたくないと感じる人たちも出てきています。その点において、サステナビリティは企業側が選ばれるための一つの要素になってきたと認識すべきかと思います。
ただ、サステナビリティを推進しよう、と言うのは簡単ですが、実際に事業をドライブしているミドル層以上と、高い社会的意義を求める若手の間には、意識のギャップはどうしても生まれてしまうものです。当社も例外ではありません。そのため、このギャップを埋める取り組みとして、若い世代に一定の権限や責任を持たせ、事業責任を持つミドル層と一緒になって仕事を進めるための仕掛けをつくっています。まだ道半ばですが、社内外からの要請が高まる中で、ミドル層以上の意識も変わってきているように思います。
―― ご著書の中では日本の大企業がサステナベーションを実践する上で重要なポイントとして、「これまでイノベーションを起こしてきた過去の技術の活用」を提示されていました。実際に、長年培ってきた技術に別の角度から光を当てることで、新たな価値を生み出した事例はありますでしょうか。
藤原氏 JVCケンウッド様の事例が象徴的です。同社はDVDやBlu-rayディスクに用いる「光ピックアップ」という技術をお持ちですが、ストリーミングの時代が到来し、DVDやBlu-rayの需要は縮小傾向にあります。そのような状況の中、「光ピックアップ」技術を活用して、がんの転移に関与している「エクソソーム」という微粒子を高精度に検出できる技術を開発されました。
今まではディスクの情報を取り出すことに使っていた技術を、がんの早期発見という全く別の目的に転用できる。これは既存の技術を使って新たな価値を生み出し、社会貢献につながっている好例です。同社の会長(当時)はもともと社外から来られた方で、自社の技術資産を別の分野でも活用するのだと、いろいろな部署を鼓舞していたそうです。経営層のこのような意識も、新たな価値を生み出すためには重要です。
社会課題を起点に発想することで、過去の技術も輝く
―― 外部からの客観的な視点を持つと見えることが、内部からの視点だけではどうしても見つけにくいように感じます。日本の大企業が新たなイノベーションを生み出すためには、どのように既存技術に光を当てていくとよいのでしょうか。
藤原氏 「この技術を何かに使えないかな?」と技術起点で考えるとおそらくアイデアは出てこないでしょう。そうではなく、世の中にある課題から、自分たちの手持ちの技術の中で使えるものはないかという視点で考えること。つまり「課題起点の発想」が求められます。
―― 大企業と比べると予算も限られる中小企業や、「自分の仕事にイノベーションは関係ない」と捉えている現場の方々が、「サステナベーション」の意識を持つためにはどのような工夫が考えられますか。
藤原氏 提供できるサービスの規模にとらわれず、社会課題の解決に役立つという実感を持つことができると良いのではないでしょうか。例えば、当社が防災システムを提供している山形県酒田市の例が挙げられます。ITリテラシーが決して高くない高齢者の方々に対して、災害時にどのように行動や避難を促していくのか。どの経路をどの手法で提示するのか、といったことを地場の中小企業様と一緒に考えながら進めています。
一つひとつのツールや手法や情報は、その地域の小さな事業者様が担っているものですが、それらを組み合わせることによって社会全体の課題解決につながる。資産や人材の制約があったとしても、事業を通して社会課題につながるのだという小さな成功体験を積み重ねることが重要だと思います。
―― サステナベーションの実現を志す日本企業に向けて、メッセージをお願いいたします。
藤原氏 日本人は、短期的な利益よりも中長期的な視点で物事を考えること、そして世の中の役に立つことに目を向けられる国民だと考えています。例えば昔から「三方良し」という考え方がありましたし、「共生」という言葉もさまざまなシーンで受け入れられてきました。そういったことは、日本から国際社会に対してもっと発信できるのではないかと期待しています。
※本記事は JBpress に掲載されたコンテンツを転載したものです
海洋プラスティックを使用したノートPC
HP Elite Dragonfly G2
重さ989g、厚さ16.1mm、CNC削り出しのマグネシウムボディーの軽量ビジネスPC。多彩なセキュリティ機能に加え、のぞき見を防止する内蔵型プライバシースクリーン、物理シャッターを備えたカメラ、コラボレーションを促進する全方位マイクなど、ビジネスに必要な全てをエレガントなボディーに備えました。
- Windows 11
- 第11世代 インテル® Core™ i5 / i7 CPU
- オンボード8GB / 16GB LPDDR4X
- 256GB / 512 GB SSD ストレージ











