AMDの次世代AI PC「HP EliteBook X G1a 14 AI PC」の実証実験を通じ、AI活用のあるべき姿を模索しはじめた三豊市教育委員会
2025-07-31
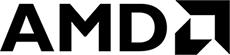
ICT教育や学校DXを進める上で、注目されているのが「生成AI活用」だ。しかし、これを校務や学びに活かすにはいくつかのハードルが存在しており、教育委員会や学校が様々な方法を模索しているというのが現状だ。今回はHPの最新AI PCを題材に、最先端のハードウェアテクノロジーを使いどのような活用方法があるか検証を始めた香川県三豊市教育委員会に話を伺った。
取材:中山 一弘

先進的な取り組みを続ける三豊市教育委員会
香川県三豊市は四国の内海に接する位置にあり、海・山・田園のすべてが揃い、自然と調和した暮らしやすい環境にある街だ。温暖な気候と豊富な産物で多くの人々が訪れる観光にも適した土地であり、特に「フルーツ王国」と呼ばれるほどあらゆる果物が周年楽しめるのも魅力のひとつだ。子育てにも最適な市であり、充実した支援も受けられ、現在小学校は19校、中学校は7校と学びの環境も充実している。※学校数は2025年7月現在
「三豊市教育委員会では、GIGAスクール構想をはじめ、ICT教育に力を入れています。子どもも大人も、夢や希望を抱き続けることができる環境を常に提供できるよう、そのための環境づくりを続けており、子どもたちには人と人とのつながりや豊かな自然環境を大切にする心と、夢や希望を実現するための知性、感性、創造力に富んだ人材育成をしていきたいと考えています」と理念を語るのは三豊市教育委員会事務局学校教育課 主任 林 和樹氏(以降、林氏)だ。
そんな三豊市教育委員会では、ICT教育の施策のひとつとして「AI活用」についていち早く取り組んでいきたいと考えていたのだという。「2024年度には、学習系、校務系端末を統合したゼロトラスト基盤の導入を本格的に進めるため、その一環として低コストなゼロトラストPCの採用を始めたり、様々な施策を続けてきました。中でも今後、生成AIは必ず学びや校務に必要になってくるテクノロジーだと考えています。ただし、これまではハードウェア、ソフトウェアが揃いきっておらず、将来的な構想を練る段階にあったと思います。しかし、2025年に入ったころから、ハードウェアが著しく進化し、AI時代にふさわしい製品が次々と発表されるようになったと感じています」と林氏は語る。
これまでの生成AIは、一般的にクラウドサービスから提供されるもので、広くインターネット上にあるあらゆるデータが情報源となるため、これを学びに活かすには一時的にでも学校内の情報がクラウド上へアップロードされる懸念があった。そのため必ずしもセキュアな環境とはいえないことから採用に踏み切れない自治体や学校が多かったが、現在は学校内の限られた環境の中で完結できる「ローカルSLM/LLM」「ローカルRAG」といったツールも出始めており、機密情報や個人情報を取り扱う組織や企業、団体から大きく期待されるようになっている。
「実際にWeb会議ツールや、Windows のサービスの中にもAIを用いた機能を持つものが目立つようになりました。まだ一斉導入とはいきませんが、試験的にAI PCを導入し、どのような可能性を持つのか検証することは可能だと考えはじめました」と林氏は語る。その思いを聞いた、三豊市教育委員会のITディレクターを務める奥野 克仁氏(以降、奥野氏)とHPは、最新のAI PCによる実証実験を提案。三豊市教育委員会の承諾のもと、AI活用の未来を試すべく、検証作業を開始することになった。
次世代AI PCのハイエンドモデルで挑む実証実験
「現在、各PCベンダーから様々なAI PCが提供されています。大きな特長としてCPU、GPUに加えAIの演算処理に特化したNPUを持っていることが挙げられます。これにより、AIツールを使った場合、それぞれのプロセッサが最大効率で動作することができ、パフォーマンスの向上と、低消費電力の両立を可能としています」と語る奥野氏。
「NPUの処理能力を図る指標として『TOPS』というものがあります。一般的にいわれる名称は『AI PC』ですが、基本的にNPUが搭載されているモデルがそのように呼ばれます。もうひとつマイクロソフトが提唱している規格もあり、そちらは同社のAIにちなんで『Copilot+ PC』と呼ばれますが、こちらには40TOPS以上あることというNPUの性能の下限が示されているのが違うところです」と解説するのはHPの三浦氏だ。
今回、三豊市教育委員会に提供されたのは「HP EliteBook X G1a 14 AI PC」で、AMDの最新モデル「AMD Ryzen™ AI 300 プロセッサ」を搭載しているのが特長となる。「このプロセッサはNPUの処理能力が55TOPSという、現時点で最高水準に達しているモデルです。まさに三豊市教育委員会様の今回のコンセプトに最適な製品だといえます」と三浦氏。
14インチクラスのボディはやや重めの約1.497kgだが、これには大きな理由がある。「これだけ処理能力の高いプロセッサですから、通常の筐体ではなく、ワークステーションクラスのエアフローレイアウトを持つ筐体が必要です。そのため、やや重くなりましたが、100%負荷をかけた状態で長時間稼働を続けても安定した動作を実現しています」と三浦氏は続けて語る。
「メモリも32GBと十分ですし、Web会議が快適になる機能が搭載されているのも気に入りました。持ち運びについてもこの重さに慣れてしまえば問題なく、逆に安心感があるノートPCだと思います」と林氏もファーストインプレッションを語る。
また、学校で活用することを考えるとセキュリティにも気を使いたいところだが、HPの法人向けノートPCには最初から統合セキュリティソリューションの「HP Wolf Security」がプリインストールされている。「HP Endpoint Security ControllerをはじめとしたBIOSレベルを含めた各階層の保護が実装されており、エンドポイントセキュリティを強く意識されている三豊市様のご期待にもお応えできる端末となっています」と三浦氏。
その他にもAI搭載のツールは豊富にプリインストールされているが、今回はより高度なAI活用を見据えて独自にHPオリジナルのローカルRAGが搭載されている。「現在はHP eSIM ConnectのQ&A のみに対応していますが、その内容を校務やICT支援員へのQ&A と置き換えて考えれば、おおよその感触はつかめると思います」と奥野氏。
「一般的に使われているクラウドサービス型の生成AIは、どうしてもインターネット回線を通じたデータのやり取りになるのでレスポンスは通信回線の状態に依存します。一方のローカルRAGやローカルSLM/LLMはサーバも端末も学校内ネットワークの内側にあるためレスポンスは常に良好です。セキュリティに関してもネットワークの外にデータは出ていかないので安全に運用できる点も特長といえます。これらの特長を見てもローカルで扱う生成AIが学校教育に最適な理由がお分かりいただけると思います」と同氏は続けて解説する。ローカル環境にある生成AIの場合、ファインチューニングなども自分たちでおこなうことができるため、必要に応じて成長させられるのも利点だといえる。
順調な滑り出しを見せた実証実験
これらに加えて、Windows には Copilot と連動する「リコール機能」や「画像生成」機能などもあるので、実証実験の環境としてかなり手応えのある仕様といえる。「実際に試験運用をしていますが、確かにいえるのはバッテリーの持ちがよくなっているということです。これはNPUによるAI機能使用時の消費電力が最適化されたものだと思いますが、Web会議が増えている現状を考えれば機能的に大きなアドバンテージになると考えます」と林氏。先ほど紹介したように、Web会議ツールの各機能やHPオリジナルのセキュリティ機能などには、そもそもAIを使ったサービスも多く、NPUによる恩恵は日常的な操作だけでも得られることが分かる。
「肝心のローカルRAGですが、あえてWi-Fiを切ってスタンドアロンPCとして使ってみましたが、予想以上にレスポンスよく反応してくれます。今回は試用版とのことで、フルスペックではないものの、定型とはいえかなりの情報量であるはずなので、校務や学びでの活用へ向けた手応えは感じることができました」と林氏は語る。今後もローカルSLM/LLM、ローカルRAG製品は増えていくことが予想できるだけに、生成AI活用に期待が持てる滑り出しといえるだろう。
「全体的にAMD Ryzen™ AI 300 プロセッサのおかげだと思いますが、Officeアプリケーションなどの日常で使うサービスやWeb会議が非常に軽快に動くのが印象的です。トータルパフォーマンスが高いため、それほど巨大な言語モデルでなければローカル環境でAIを動かした場合でも大きな負荷は感じないかもしれません。いずれにしても実証実験の期間はまだありますから、もっと可能性を探ってみたいですね」と林氏は期待を語ってくれた。HPは引き続き三豊市教育委員会のAI PC活用の実証実験を見守り、必要なサポートを提供していく。
※本ページに記載されている情報は取材時におけるものであり、閲覧される時点で変更されている可能性があります。予めご了承下さい。
※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。











