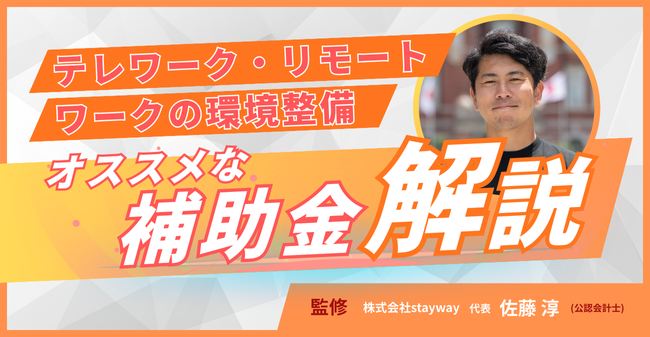HP Tech&Decive TV 以外のコンテンツも検索対象となります。
2022.09.05
DXの入り口となるペーパーレス化。その重要性とメリットを解説
必要性が叫ばれて久しいペーパーレス化。コロナ禍によって紙を中心とした業務の問題点が浮き彫りになったことや、世界中で環境保全の気運が高まっていることや法制度も後押しし、ペーパーレス化の必要性はますます高まっています。本記事では、ペーパーレス化や電子化との本質とはなにか、ペーパーレス化がどのような将来につながるのか、メリットやデメリット、推進方法や企業の取り組み事例について解説します。
1. ペーパーレス化、電子化とは

紙を使用しない状態を意味する「ペーパーレス」。「ペーパーレス化」とは、業務上で使用する紙を削減する取り組みのことです。また、ペーパーレス化と似た意味で使われる言葉に「電子化」があります。電子化とは紙をスキャナーやカメラで取り込み、PDFなどのデジタルデータに変換することです。
ペーパーレス化の取り組みとしては、次のような例があげられます。
- 書類のPDF化
- クラウドストレージや文書管理システムを使用した一元管理
- ワークフローシステムや電子契約システムの活用 など
紙を使用した業務の問題点は、印刷や郵送、スキャン、文書管理などにコストや労力がかかることです。さらに、過去の大量な情報を活用できないまま眠らせてしまうというデメリットもあります。
情報技術が発達した昨今、紙の役割の多くはデジタルで代替可能です。ペーパーレス化によって、社内業務の省力化や自動化、法対応がしやすくなるなど、さまざまなメリットがあります。
さらに、ペーパーレス化はDX(デジタルトランスフォーメーション)の入り口にもなります。OCR(光学式文字認識)を活用しスキャンした紙文書をデジタル化し、編集・検索可能にすれば、これまで眠らせていた情報をデータとして活用できるようになります。こうすることで資産の有効活用が進みます。また、このデータをAIと組み合わせ、ワークフローの自動最適化や企業資産の高度な管理と活用を施すことで、より多くの付加価値を産み出すことも可能となるでしょう。
2. なぜペーパーレス化が必要なのか

ペーパーレス化はなぜ必要なのでしょうか。その背景について説明します。
① 政府が後押しする電子化
政府は以前から、「電子帳簿保存法」や「e-文書法」の施行など、働き方改革の中でペーパーレス化を推進してきました。近年、DXやコロナ禍におけるテレワーク推進により、さらに政府の後押しは強まっています。
具体的にはどのような動きがあったのでしょうか。2020年に経済産業省が発表した「DXレポート2」の中で、企業は業務プロセスのデジタル化に直ちに取り組むべきだと提起し、電子化やペーパーレス化を例にあげています。2021年には、行政手続きの押印を廃止する「脱ハンコ」法案が可決し、日本のデジタル化を推進するデジタル庁も発足しました。2022年1月には「電子帳簿保存法」が改正され、要件の緩和やメリットの追加がなされました。2年間の猶予はできたものの、2024年1月には義務化されます。
日本のデジタル化はアメリカなどの先進国と比較して遅れているという指摘もあり、今後も政府によるペーパーレス化や電子化推進の動きは益々強まると考えられます。
参考・出典:DXレポート2(中間取りまとめ)|経済産業省
(https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004-2.pdf)
② 世界規模のカーボンニュートラルへのシフト
近年、環境破壊による気温上昇や災害リスクの高まりが予測されています。その中で世界的に注目を集めているのが、「カーボンニュートラル」や「持続可能な開発目標(SDGs)」などの考え方です。企業がどのくらい環境に配慮しているかを評価する投資家も増えています。
紙を大量に消費する組織活動を続ければ、間接的に環境を破壊することになります。なぜなら、紙の材料となる木の伐採が無計画に進むことで、焼却によるCO2の排出がコントロールできない量として増えていくからです。日本は、国民一人当たりの紙の消費量は世界でもトップクラス。カーボンニュートラルやSDGsの観点からも、ペーパーレス化に取り組み、計画された適切な量と質への転換を図る必要があるのです。
関連リンク:カーボンニュートラルに向けた2030年目標と具体的な企業の取り組みとは?
(https://jp.ext.hp.com/techdevice/sustainability/planet_sc40_06/)
③ ハイブリッドワークなど多様な働き方への対応
コロナ禍を経て、テレワークと出社を組み合わせた「ハイブリッドワーク」が一般的になり始めています。多様な働き方が注目される一方で、押印のための出社など、紙やオフィス出勤をベースとした業務プロセスの問題点が明確になりました。
企業がハイブリッドワークへ対応するには、働く場所の制約はできるだけ少なくし、業務を進められる体制や環境を整備しなければなりません。多様な働き方を実現するためにも、ペーパーレス化は必須課題といえるでしょう。
④ 生産性向上へのアプローチ
生産年齢人口が減少している日本では、生産性向上は非常に重要な課題です。2030年には644万人分もの人手が不足するという推計もあり、近い将来さまざまな業種で人手不足への対応を迫られるでしょう。
ペーパーレス化は、生産性向上へのアプローチとして有効な手段です。文書を電子化し、業務フローをデジタル化することによって、文書管理や検索の工数削減などの省力化が実現できます。さらにデジタル化したデータを活用すれば、RPAを使用した業務自動化や、AIを使用したワークフローの自動最適化なども可能となります。ペーパーレス化の取り組みが、生産性を高める高度な技術活用の入り口となるでしょう。
参考・出典:労働市場の未来推計 2030|パーソル総合研究所
(https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/)
3. ペーパーレス化のメリット

ペーパーレス化にはたくさんのメリットがあります。具体例を5つご紹介します。
① コスト削減
紙を使用した業務には、さまざまなコストがかかっています。実際に経費がかかっている「目に見えるコスト」だけではなく、担当者の手間や時間といった「目に見えないコスト」も多く発生しているのです。ペーパーレス化に取り組むことによって、経費だけでなく人的コストの削減にもつながるでしょう。
ペーパーレス化によって削減できるコストには、次のような例があります。
目に見えるコストの例
- コピー用紙やインク、ファイルなどの消耗品のコスト
- 過去の文書を保存するスペースのコスト
- 廃棄するためのコスト
- プリンターを使用する電気代やメンテナンス費
- 郵送費 など
目に見えないコストの例
- 消耗品の発注や管理に関わる業務工数印刷する時間
- 共有・提出のための移動時間
- 文書の管理・検索工数 など
② 生産性向上
ペーパーレス化によって期待できる生産性の向上には、大きく分けて2つの段階があります。
ひとつは、文書の電子化や業務プロセスのデジタル化による業務効率化です。社内業務を迅速に行えるほか、業務を変更する際にもスムーズに対応できます。
業務効率化の例
- 社内業務の自動化
- 省力化による人的工数削減
- 業務変更時の迅速な対応
- 文書保存における法対応
もう一つは、価値創造につながるデータ活用です。従来紙で保管していた情報をデジタル化することで、新たな付加価値を生み出す情報として活用できます。
データ活用の例
- 過去データの集計、分析
- AIを活用した予測
- 社内に点在するナレッジの管理(Enterprise Contents Management)と活用
③ 柔軟な働き方の実現応
紙を使用した業務では、業務を遂行するためにオフィスに行かなければなりません。情報がアナログで管理されている場合、過去の重要な情報を見るのにも紙の保管場所に移動する必要があります。この物理的な制限が、働く環境の多様化をさまたげている原因のひとつです。
ペーパーレス化をすれば業務遂行や情報共有のための物理的な制限がなくなり、テレワークやハイブリッドワークが可能となります。場所にとらわれる必要がなくなれば、社員のワークライフバランス向上や、遠方に住む人材の活用につながります。
④ セキュリティ向上
オフィスにある文書の中には決算書類や仕様書など、機密情報を含んでいるものも多いため、セキュリティ対策が欠かせません。紙のセキュリティ対策は、鍵付きのキャビネットや金庫などでの物理的な管理となり、盗難や災害により紛失するリスクもあります。また、「◯◯(役職)以上しか閲覧できない」などの権限を持たせたい場合、鍵の管理が主な手段となり、業務が滞ったりトラブルのもととなってしまいます。
資料をデジタル化することによって、次のようなメリットがあります。
- 資料にパスワードを設定できる
- 万が一ファイルが流出しても暗号化によって情報漏洩を防げる
- アクセス権限(閲覧・編集など)を設定できる
- アクセスログを管理できる
⑤ AIによる自動プロセス改善
定型処理を省力化するための活用としても技術発展が進んできたAI。しかし、AI技術は日々進化を遂げており、これまでは難しいとされてきた自然言語処理や人間的な判断もできるようになってきています。
業務のデジタル化は、AI活用の入口にもなります。ワークフローをデジタル化した上でAIを活用すれば、AIが業務プロセスを分析し、自動的に最適化することも可能になるのです。OCRによる文書の自動分類から始まり、業務フローの見直しや改善といった工程も、AIによって省人化できるようになるでしょう。
⑥ BCP対応
ペーパーレス化し、データをクラウドなどに保存することで、BCP対応につながります。BPCとは事業継続計画(Business Continuity Plan)の頭文字を取ったものです。災害や今回のパンデミックのような状況に陥った際、紙がベースの業務フローのままでいると、請求や受発注、契約といったビジネスの根幹をなす業務の遂行に大きな支障が出るリスクがあります。
ペーパーレス化することで、在宅でも業務を遂行でき、災害時のスムーズな業務復旧につなげられます。
4. ペーパーレス化にデメリットはあるのか?
ペーパーレス化には基本的にはデメリットといえるものはありません。メリットの方が大きいため、政府も推進しています。
ただし、データ化によってあらたに対策をしなければならないリスクもあります。たとえばサイバー攻撃やサーバーダウン、システム障害、通信障害などです。万が一に備えたセキュリティ対策やバックアップなどの対策強化は必要といえるでしょう。
5. ペーパーレス化を推進する方法
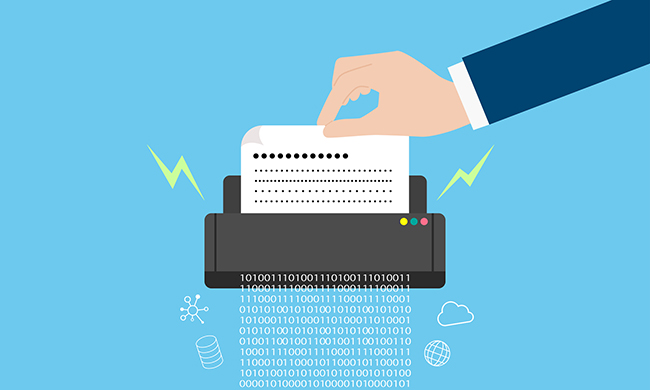
ペーパーレス化には、基本的に2つのアプローチがあります。ひとつは、既存の紙の文書を電子化すること。もう一つは、紙を使わない業務フローを構築することです。
紙を使わない業務フローを構築できれば、大幅に紙を削減できます。しかし、いきなりすべてをペーパーレス化するのは難しいこともあるでしょう。その場合は、文書の電子化から段階的に取り組むことが大切です。
ここでは、ペーパーレス化を推進する方法について解説します。
① 業務フローを明確にする
まず、現在紙が発生している業務について、業務フローを洗い出します。
業務の目的やゴールを明確にしておくとよいでしょう。
② 業務フロー上のドキュメント(文書)をリスト化し対象を定める
業務フロー上で発生するドキュメントをリストアップし、電子化の対象を定めます。
誰がどのような目的を果たすために発生しているのかを確認しておきましょう。そうすることで、電子化やシステム化で代替できるかどうか検討しやすくなります。
③ クラウドサービスなど電子化に必要なツールを導入する
業務の目的が達成でき、かつペーパーレス化できる方法を検討し、必要なツールを導入します。
例)
- 承認、契約業務…ワークフローシステム、電子契約システム など
- 保存、管理業務…クラウドストレージサービス、文書管理システム など
各業界からさまざまなクラウドサービスが出ています。上手に活用すれば、ソフトウェアの導入費やメンテナンス費を抑えることも可能です。
④ 紙のスキャン環境やプロセスを可視化する
フロー全体をペーパーレス化できる業務ばかりではないでしょう。どうしても紙が発生する場合、紙をスキャンしPDFにした上でシステムにアップロードするなど、部分的なペーパーレス化が想定されます。とくに他社とのやり取りではさまざまなフォーマットで書類が送られてくるため、紙をスキャンしなければならない場面が多いでしょう。
ハイブリッドワークが普及した現代では、オフィス環境以外、つまり自宅や外出先でのスキャンも想定しなければなりません。その際のリスクや、環境整備についても考えておく必要があります。
たとえば、文書の検索性向上やデータ活用を視野に入れている場合、スキャン機器でOCR機能が使えるかどうかが重要です。また、スマートフォンやデジタルカメラなどでもスキャンは可能ですが、セキュリティ面でのリスクも考えられます。
社内外における紙のスキャン環境やプロセスを可視化し、最適化しましょう。
6. ペーパーレス化に取り組む企業の例
ペーパーレス化に積極的に取り組み、効果を高めている企業の事例についてご紹介します。
① 第一三共グループ
医薬品の研究開発、製造、販売等を行う第一三共グループ。「競争力と優位性を生み出す多様な人材の活躍推進と育成」を目指す取り組みとして、総務・人事・DX部門を統合し、「DS Smart Work」を推進しています。社員の生産性とエンゲージメントを高めるため、最適な働き方を選択できる環境整備に取り組んでいます。
経費精算システムの刷新や押印廃止など、IT基盤の強化を積極的に行い、紙に依存しないワークスタイルを実現。ペーパーストックを46%削減し、オフィスの有効活用にも取り組んでいます。2010年から段階的にテレワークを導入し、2020年の調査では約8割の社員が生産性に問題なしと回答。また、エンゲージメントスコアもベンチマークを大きく上回り、効果的な取り組みとなっています。
参考・出典:『働く、が変わる』テレワークイベント 表彰受賞企業 取組紹介 講演予稿集|厚生労働大臣表彰 輝くテレワーク賞
(https://kagayakutelework.jp/symposium/pdf/report/1130k_proceedings211130.pdf)
② 伊藤忠テクノソリューションズ
コンピュータ・ネットワークシステムの販売・保守や、ソフトウェア受託開発などを行う伊藤忠テクノソリューションズ。コロナ禍を契機にハイブリッドワークを展望することになりました。社内システムの多くはすでにペーパーレス化していましたが、オフィス内の書類は推定5,000万枚にも及んでいました。オフィスの総面積を縮小し、コミュニケーションエリアを増設するため、オフィス内書類の75%を削減したそうです。
緊急性や重要性の高い書類30万枚を電子化し、大量の文書の中からでも探しやすいように工夫。「アクセスできればよいもの」と「閲覧頻度や情報価値の高いもの」に分類し、後者については日付や案件名がわかるファイル名にするなど、文書管理における検索性を高めています。
参考・出典:オフィスの書類の75%は「断捨離」可能 伊藤忠テクノソリューションズのペーパーレスの秘訣|ログミーBiz
(https://logmi.jp/business/articles/326180)
7. まとめ
ペーパーレス化は生産性向上を目指す企業や組織にとって必須です。ペーパーレス化に取り組む際には、文書の電子化やワークフローのデジタル化だけではなく、社内外における文書の取り扱いや入出力環境にも配慮する必要があります。
HPのMPSはサービス、ソフトウェア、ハードウェア、サプライをトータルでサポートするサブスクリプションサービス。印刷環境の可視化・最適化だけでなく、ワークフローの最適化やセキュリティ向上などへも貢献します。とりわけ物理世界からデジタル世界へと転換させるスキャンというプロセスは今後の業務フローを考えるにあたって重要な要素となります。またハイブリッドワークの普及に伴い、スキャン環境がオフィスに留まらないことも意識しなければなりませんが、HP MPSはそのような環境構築にも対応しています。詳しい情報はホワイトペーパーでぜひ確認してください。
下記必要事項を記入の上、ボタンを押してください。