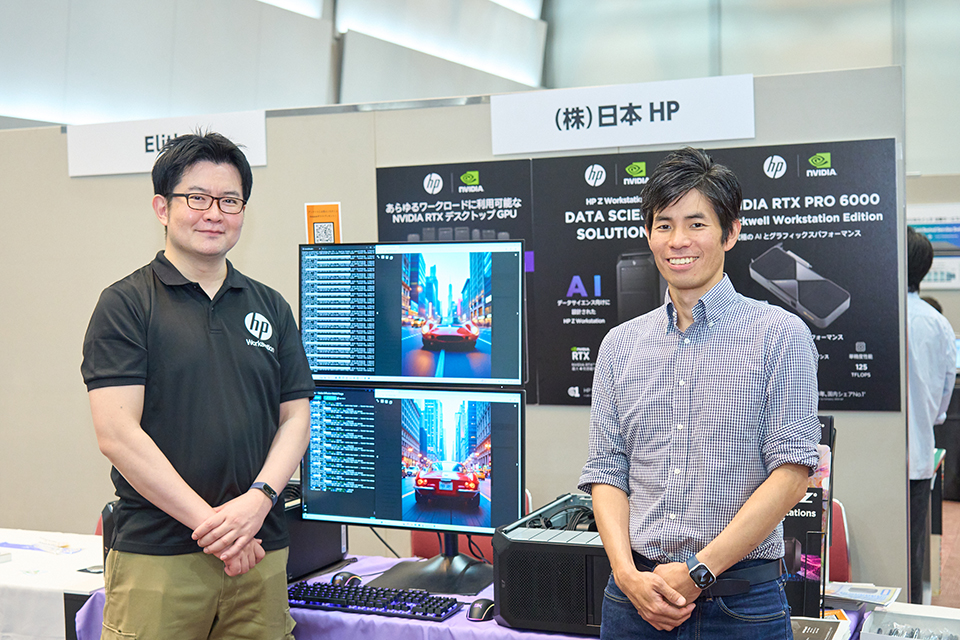HPワークステーションで構築するローカルSLM/LLMを「2025年度 人工知能学会 全国大会」で発表
2025-08-27
2025年5月27日~30日、大阪国際会議場で「人工知能学会 全国大会」が開催された。今回で39回目となるイベントで、国際セッション、一般セッション、オーガナイズドセッション、ランチョンセミナーなどが用意され、オンライン発表を含めたハイブリッド開催となったことでも話題を集めた。HPはもちろんこの大会に参加。ワークステーションで構築するローカルSLM/LLMをテーマに講師を招いてのセミナーや展示で会場を沸かせた。それでは当日の模様をダイジェストで報告しよう。
SLMの可能性を追求
様々なセッションが用意される人工知能学会のイベントだが、HPプレゼンツとなったのは上智大学大学院 応用データサイエンス学位プログラム 深澤 佑介准教授による「説明可能なSLM(eXplainable SLM:XSLM)の可能性と未来の展望」と題されたセミナーだ。
NTTドコモに19年在籍し長年データサイエンスの研究開発に携わってきた深澤氏は入社当時から人工知能に興味を持っていたという。「前職では人工知能の中でも特にデジタルデータに対して機械学習を用いた予測や推定に取り組んできました。そんな私がアカデミアに移籍し、何をしているのかというと、機械学習に代わってLLMによる分類や予測ができないかを研究しています。ヘルスケアや防災などの実世界のデータでは少量かつ説明変数が多いことが多く、従来の機械学習で精度のよいモデルをつくることは難しいのです。一方で、大量のデータで事前学習したLLMであれば少量データでも精度を上げることができるのではないかと考えています。」と深澤氏。
同氏はヘルスケアや防災などの領域での研究を進めている。例えば、ヘルスケア分野では、看護師のスマートフォンログからメンタルヘルスの予測や、感動体験と身体的健康度の関連性の研究を行っている。防災領域では、近年被害が相次いでいる秋田県における熊の遭遇予測や、登山をした場合の遭難リスクの分析など、社会課題に直結するようなテーマに対して、AIの手法を使った研究を推進している。
「私はHPより、同社のワークステーション『HP Z6 G5 A Workstation』を提供していただき、テストを続けてきました。物理コア数が多い、AMD Ryzen™ Threadripper™ PROプロセッサや、ハイエンドグラフィックスNVIDIA™ RTX 6000 Adaを1基搭載するなど、リッチなスペックのコンピューターです。これを使って予測モデルを構築し、計算速度や搭載可能なLLMがどれぐらい増えるかなどを確認しています」と深澤氏は語る。
同氏が上智大学に着任したのが2023年。以前から機械学習の研究を続けてきた中、この頃を境に状況が一変したのだという。「分類や回帰問題を解くにはこれまでは機械学習が中心でしたが、LLMを用いたプロンプトベースの予測モデルが登場し始めました」と深澤氏。プロンプトに直接データをそのまま入れて予測や分類を行っていくスタイルに大いに興味が湧いたのだという。
「LLMと機械学習を比較してみるとどうなるのか。例えば出力の説明性について、LLMはブラックボックス性が強く、機械学習は説明可能なAIの技術を使えば比較的解釈しやすいということがいえます」と深澤氏。精度の高い機械学習を研究し続けてきた深澤氏にとって、LLMの手法は説明可能の観点で当初違和感があったのだという。「現在、LLMの入力と出力のペアを用いて、LLMの分類結果を解釈するという方法を研究しています」と深澤氏は自身の考えを語る。
深澤氏はここで話題を変え、言語モデルのデータサイズについて語り始める。「LLMに関しては、現在パラメータ数は1兆(1trillion)を超えていますが、このサイズになるとかなり大規模なコンピューターが必要です。一方で10億(1billion)から100億(10billion)ぐらいまでのパラメータ数であるSLMは市販のパソコンでも学習できるぐらいのサイズ感です」と深澤氏。
LLMの維持にかかる電力問題は以前からニュースになるほどだが、SLMなら手元で運用することもできる。「アーキテクチャも進化を続けていて、コーディング用、数学用、チャット用といったように言語モデルを分けて利用するアーキテクチャも提案されています」と語る深澤氏。さらに同氏は「ここ最近では爆発的な量のパラメータ数で処理するより、質の高いデータだけを学習データとして用いたり、蒸留などの技術を使いパラメータ数を抑えつつ、品質のよいものを作っていこうというスタイルにシフトしているのではないかと思います」と言葉を続ける。
深澤氏はその後、主要なSLM/LLMモデルについての試用結果や特長を発表。「今後、ビジネスの世界でもSLMやLLMを用いて分類や予測を行う可能性が広がると思います。こうした状況においては、精度向上だけでなく説明可能性も求められていくのではないかと考えています。」と深澤氏は話し、セミナーを終了した。
最新グラフィックスを搭載したフラッグシップモデルを展示
会場に用意されたHPブースでは、NVIDIAのワークステーション向け最新グラフィックス「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition」を搭載したHP Z8 Fury G5 Workstationを展示。非対応のアプリケーションが多いため、PyTorchを動作させるためソースからビルドしてグラフィックスボードに対応させ、CUDA12.8にてBlack Forest Labsが開発した「FLUX.1」を動作させていた。
「この環境で現行モデルのNVIDIA RTX 6000Adaとの処理速度比較をリアルタイムで見せるというデモンストレーションになります。ご覧の通り、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Editionでは、おおよそ2倍の速度が出ていることが分かります」と解説するのはHPの勝谷氏だ。実際に挙動をみると処理速度の体感差は2倍以上に感じる。現時点でデバイス的にもアプリケーション的にも非対応のものを、無理に動かしている状況でこの結果が確認できているので、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Editionの可能性は非常に大きいことが期待できる。
「今回のやり方の場合、マザーボードがNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Editionを認識できていないため、ファンが全開で回ってしまい騒音もかなりあります。しかし、製品版がリリースされる頃にはファンを含めてすべての機能がコントロール下に入るので、Ada世代のグラフィックス同様、ほとんど音が発生せずに運用できるようになるはずです」と勝谷氏は補足する。このデモンストレーションは会場で特に目を引き、多くの来場者が説明を求めていた姿が印象的だった。
ちょうど取材をしていたタイミングで先ほどランチョンセミナーに登壇した深澤氏が来訪。改めてHPワークステーションについて話を伺うことができた。
「研究室ではDockerを導入してGPUを動かしているのですが、その過程でGPUを認識しなくなったりするトラブルが起こることがあります。しかし、今回試用しているHP Z6 G5 A Workstationではそのような不具合とは無縁で、最後までスムーズに環境構築ができました。他社製のコンピューターと比較してファームウェアなどの仕組みがかなり堅牢に調整されていることが伺えます」と語る深澤氏。その後の運用で、かなりの高負荷作業をさせてもノントラブルが続いているのだという。
「デザインも気に入っていて、ケース上部についている取っ手が非常に重宝しています。ワークステーションは結構移動させる機会が多いのでとても便利ですね。主要なインターフェイスが前面に揃っているのも便利で、デバイスを接続して設定するようなケースで利便性が高くそこも気に入っています」と深澤氏はデザインについて言及する。
「また、モバイルワークステーションの『HP ZBook Ultra G1a 14inch Mobile Workstation』の検証もしていますが、これまで使ってきたノートPCと比べて、ファンが唸ることがほとんどありません。限界まで回っているような唸り音がすると作業をするにもプレッシャーがかかりますが、そういったこともなく快適に使えています」と深澤氏。同氏は最後に「1点だけ不満があります。せっかくすごいグラフィックスカードやプロセッサが搭載されていても外部からは見えないので、ゲーミングPCまでとはいいませんが、グラフィックスボードの位置にガラスを配置して中が見えるようにするなど、ちょっとした演出があっても良い気はしますね(笑)」と笑顔で語ってくれた。
深澤氏のセミナー、ブース展示ともに多くの来場者に高く評価された今回の人工知能学会 全国大会は終了となった。HPは今後も日本全国のイベントに積極的に参加していくので、HPワークステーションの実機デモや各種製品群に触れてみたいという方はぜひ来場していただきたい。
HPは、ビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。
Windows 11 は、AIを活用するための理想的なプラットフォームを提供し、作業の迅速化や創造性の向上をサポートします。ユーザーは、 Windows 11 のCopilotや様々な機能を活用することで、アプリケーションやドキュメントを横断してワークフローを効率化し、生産性を高めることができます。
組織において Windows 11 を導入することで、セキュリティが強化され、生産性とコラボレーションが向上し、より直感的でパーソナライズされた体験が可能になります。セキュリティインシデントの削減、ワークフローとコラボレーションの加速、セキュリティチームとITチームの生産性向上などが期待できる Windows 11 へのアップグレードは、長期的に経済的な選択です。旧 Windows OSをご利用の場合は、AIの力を活用しビジネスをさらに前進させるために、Windows 11 の導入をご検討ください。
※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。


ハイブリッドワークに最適化された、Windows 11 Pro+HP ビジネスPC
ハイブリッドなワークプレイス向けに設計された Windows 11 Pro は、さらに効率的、シームレス、安全に働くために必要なビジネス機能と管理機能があります。HPのビジネスPCに搭載しているHP独自機能は Windows 11 で強化された機能を補完し、利便性と生産性を高めます。
詳細はこちら