HP EliteBook X G1a 14 AI PCで構築するローカルSLM/LLM「商談同行AI」の実力とは
2025-01-31
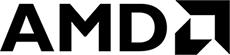
AI PCの登場により、一気に現実味が出てきた企業ナレッジを活用したローカルSLM/LLM。NPUはさらに進化し、2025年には次世代プロセッサを各ベンダーが実装するなど、話題は尽きない。そんな中、時代の先端をいくAI開発ベンダーは社会実装可能なソリューションを市場へ投入し始めている。ここでは、株式会社WEELの最新AIサービスと、HPの最新AI PCを組み合わせた事例を紹介したいと思う。
取材:中山 一弘
営業マンのスキル差を埋める「商談同行AI」
生成AIに関する受託開発やオーダーメイド開発をメインに活動を続ける株式会社WEEL(以降、WEEL)。生成AIソリューションの開発だけでなく、AI導入や活用についてのコンサルティングや研修サービスも提供しており、企業にAIが根付くまで共に歩んでくれる企業として、多くのユーザーから信頼を勝ち得ている。
「AI処理が得意なNPUを持つクライアントPCが普及するようになり、企業でもAIエージェントをローカル環境でやりたいというニーズが増えています。単純なチャットボットではなく、きちんと業務効率化が狙えるツールとしてAIを取り入れようとしている企業は日増しに多くなっている印象です」と語るのはWEEL 生成AI事業部 統括リーダー 田村 洋樹氏だ(以降、田村氏)。

生成AIがブームになった当初はクラウドサービス全盛の様相だったが、ここ最近では公開情報だけでなく、社内に保管してある自社の非公開情報をいかにAIで活用していくかが、企業競争力を高めるための大きな分岐点になると注目されている。そんな状況の中、WEELが今回提供してくれたのが「商談同行AI」だ。
「簡単にいうと、若手営業マンが顧客企業と交渉する際にAIが一緒に同行してサポートするサービスになります」と語る田村氏。これまでは先輩営業マンや上司がその役目を担っていたが、AIが代行することにより、人的リソースの最適化や若手営業マンの育成といった面でも役立つサービスということになる。
「商談同行AIをインストールしたPCで、顧客との会話をリアルタイムで文字起こしをして、それを解析。自社の営業ナレッジから類推される次のアクションを導き出し、回答を表示するというのがこのサービスの一連の流れです」と田村氏は解説する。このとき、ナレッジがPC外へ流出することはなく、セキュアな状態が保たれていることも特長となる。

若手営業マンは顧客の要望を聞き終えたと思ったときに商談同行AIのボタンを押す。通信環境や会話の量にもよるが、数十秒から数分の間に生成AIからの回答が返ってくる。自分はそれをヒントに相手に必要な情報を伝えるなどのアクションをすればよいのだ。その様子はまるで、ベテラン営業が「こういう話題を返すと顧客満足度が上がり、商談が成立しやすい」と教えてくれているようだ。
実際に商談同行AIをインストールした「HP EliteBook X G1a 14 AI PC」上のデモでは、1分未満で回答が得られた。「本来は先輩や上司がアシストしてくれる部分も、商談同行AIが補完してくれるので、若手営業マンは自信を持って営業活動が続けられます。得られる回答も企業がこれまでの成功例として貯めてきたナレッジから抽出されたものなので、それなりの品質のものになります」と田村氏は語る。
営業的なメリットが非常に高いサービスだが、この仕組みを実現するには商談中の文字起こしに加え、社内の機密情報を取り扱うためのSLM/LLMモデルが常に動いていることになる。機密情報以外の一般情報はクラウドから取り寄せるので問題ないが、やはりこのサービスを動かすPCにはそれなりの処理能力が求められることになる。

「例えばAIエンジンを搭載した初代の AMD Ryzen™ PRO 7040 シリーズプロセッサのNPUの処理能力は10TOPSでした。これでも動きますが、現在主流の AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズプロセッサになると最大55TOPSと大幅に演算性能が向上しています。これぐらいの処理能力があれば、商談同行AIのレスポンスも体感できるレベルで違ってきます」と解説する田村氏。実際のサービス活用においては、NPUだけでなくCPUやGPUも利用するので、やはり最新スペックのPCを使うのが生成AIをストレスなく利用するためには必要だといえる。
HP EliteBook X G1a 14 AI PCの実力は?
さて、ここからは今回のテストケースに使用したHP EliteBook X G1a 14 AI PCについて、製品担当の株式会社 日本HP パーソナルシステムズ事業本部 クライアントビジネス本部 CMIT製品部 部長 岡 宣明氏に話を伺っていきたい。

まず、概要としてHP EliteBook X G1a 14 AI PCだが、「 AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズプロセッサ」を搭載していることが特長となる。上位モデルの「 AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 375 」の場合、12のCPUコアと16のGPUコアにより、28の論理コアを実現している。さらに、NPUはクラス最強の最大55TOPSを誇り、CPU/GPU/NPUをバランス良く配置している。
「この55TOPSはHPでなければ出せない数値になります。AMDと共に開発を進めてきたプラットフォームでしか実現できないAI処理能力の高さは、このモデルの最大のアドバンテージになります」と岡氏は解説する。
品のあるグレイシャーシルバーの筐体はワークステーションと同じものを採用しているという。「55TOPSという高速処理をするわけですからそれなりの熱も出ます。モバイルワークステーションはディスクリートグラフィックスやCPUを100%の利用率で長時間稼働させることを前提としているため、熱管理に優れた独自のデザインを採用しています。そのデザインをHP EliteBook X G1a 14 AI PCにも採用しているので、酷使した場合でも高い安定性をもたらします」と岡氏は語る。
モバイルワークステーションと同じ筐体を手に入れ、 AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズプロセッサの実力をいかんなく発揮できるHP EliteBook X G1a 14 AI PCは、単なるモバイルノートPCとしてだけでなく、負荷の高い作業が多い情報システム部や経営者、さらには開発系のスタッフまで、マシンを酷使する職種にも最適なコンピューターだといえる。
さらに価格帯について以前のフラッグシップモデルよりも抑えられているというので驚きだ。「2024年までの法人向けノートPCのフラッグシップモデル『HP Dragonfly』シリーズよりも、低い価格帯での販売になります。当時の最終モデルよりもHP EliteBook X G1a 14 AI PCはAI以外のトータルパフォーマンスも向上していますから、コストパフォーマンスは非常に高いと考えています」と岡氏は自信をのぞかせる。
また、HP EliteBook X G1a 14 AI PCにはすでに多くのローカルAI機能が搭載されているWebコラボレーションを支援する機能も満載している。「Webカメラには『Poly Camera Pro』が採用されており、ユーザーの存在を常に認識し、オートフレームやピントの集中をしています。バーチャル背景なども含め、これらの機能はNPUを使用するため、バッテリへの影響は最小限です」と岡氏。

Poly Camera Proには高いセキュリティ機能も搭載されており、Windows Helloに登録されている以外の人間がディスプレイ前にくると、自動的に画面にシャッターをかけることができる。カフェで仕事をしている最中などで背後から画面をのぞき見られるショルダーハッキングなどにも対応できるのはハイブリッドワーク時に心強い仕様といえる。
できるだけ早期から使いこなしたいAI PC
「HPの法人向けノートPCは非常に多くのベンダーのISV認証を受けています。つまり正常動作することを私たちHPとアプリケーションの発売元が検証しているのです。今後、『商談同行AI』のようなローカルAIがますます市場に出てくるでしょうし、既存のアプリケーションにもAI機能の実装が進んでいます。AIによる恩恵をいち早く受け取れるよう、いまからでも最先端のAI PCに触れておくことをおすすめしたいですね」と岡氏は語った。

「『商談同行AI』は営業活動だけでなく、様々なシーンで活用できるソリューションになると考えています。例えば、店舗の接客、病院の診察などが考えられますが、調剤薬局でお薬を引き渡す際の接客などは、現場で録音はしているものの資料として残す際にテキストの打ち直しなどが多いと実際にご相談があった案件もあります。いただいたお話を要約し、それに対する回答を得るためにボタンを押す。これだけで、いつの間にかお客様が欲しがっている商品のリストや、患者のカルテが出来上がっている、あるいはお薬で悩んでいる方への対応を促すアドバイスが出てくるのですから、現場の方の負担は大きく軽減できるはずです。ほかにもAIがみなさまをサポートできることはまだまだたくさんあります。AI PCの進化と共に、やれることも広がると思いますので、みなさまもお悩みのことやアイデアがあったらぜひお気軽にご相談ください」と最後に田村氏は語ってくれた。

AIが活躍するシーンは今後もますます多くなることは確実だ。必要となってから環境を作るよりも、可能性を見出すためにまずはAI PCを使ってみるところからはじめてみるのもよいだろう。特にローカル環境でのAI活用はアイデア次第で企業価値を大きく高めることが期待できる。AI活用が当たり前になる時代はすぐ目の前にきている。すべての企業は早期に準備を始めることをおすすめしておきたい。
※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。





