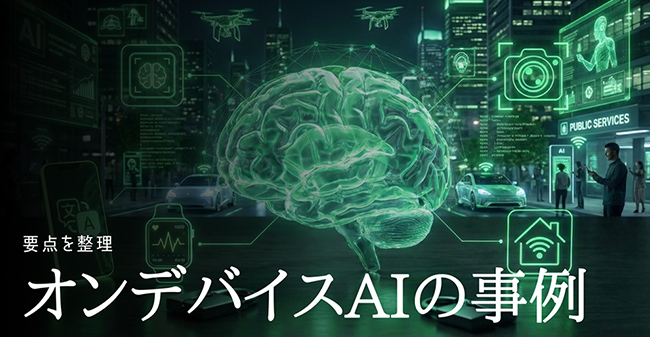ビジネス現場で話題の「Dify」超入門編
2025-09-18
「生成AIを試してみたけど、一時的な利用で終わってしまった…」「自社の業務に合わせてAIを活用したいけど、開発の知識がない…」
そんな経験はありませんか?
生成AIは「試すだけで終わる」ケースが少なくありません。しかし、Difyは、プログラミング不要(ノーコード)でAIアプリを設計し、社内に展開・運用まで完結できる、まさに現場のためのAIプラットフォームです。
本記事では、この革新的なツール「Dify」について、専門知識がなくても扱えるポイントに絞り込み、費用感や簡単な導入手順を交えながら、分かりやすく解説します。
ライター:國末拓実
編集:小澤健祐
Difyとは何か
Difyは、AIアプリケーションの開発と運用を、誰でも簡単に行えるように設計されたオープンソースのプラットフォームです。その最大の特徴は、専門的な知識がなくても、自社の業務に合わせたAIツールを構築できる点にあります。
ノーコードでAIアプリを構築できる
Difyの最も大きな魅力は、ノーコードでAIアプリを開発できる点です。
- 直感的な操作: プログラミングコードを書く代わりに、機能を持つブロックをドラッグ&ドロップでつなぎ合わせるだけで、AIの動作フローを視覚的に構築できます。
- 専門知識不要: AIに関する深い知識がなくても、「こういう時に、こう動いてほしい」というビジネスの要件を、そのままアプリの形に落とし込むことが可能です。
ChatGPTとの違い:共有・運用までワンストップ
ChatGPTが主に「個人」の対話ツールであるのに対し、Difyは「チーム・組織」での利用を前提としています。
| 比較項目 | ChatGPT | Dify |
|---|---|---|
| 主な用途 | 個人の情報収集、アイデア出し、文章作成 | チームでの業務自動化、社内ナレッジ共有、顧客対応 |
| カスタマイズ | 限定的(プロンプトの工夫が中心) | 高い(自社データの連携、業務フローの設計) |
| 共有・運用 | 作成したプロンプトの共有は手動 | 作成したAIアプリをURLで簡単に共有。利用状況の分析や改善もプラットフォーム上で可能。 |
Difyは、AIアプリを「作って、共有し、改善する」という運用サイクル全体を、一つのプラットフォームで完結できる点が、ChatGPTとの決定的な違いです。
覚えておきたい3つのキーワード
Difyで何ができるのか?まずは、ビジネスで特に役立つ以下の3つのキーワードを覚えておきましょう。
- チャットボット: ユーザーからの質問に自動で応答するAI。
- 検索強化(RAG): 自社の文書やデータをAIに学習させ、それに基づいた正確な回答を生成させる技術。
- 作業自動化(ワークフロー): 複数のステップからなる定型業務をAIに自動で実行させる仕組み。
Difyは、これらの機能を組み合わせることで、様々な業務課題を解決します。
ビジネスシーン別の活用イメージ
では、Difyを使って具体的にどのような業務改善ができるのでしょうか。ここでは、すぐにイメージできる3つの活用シーンを紹介します。
社内FAQを即席チャットボット化
社内の問い合わせ対応は、多くの部署で負担となっています。Difyを使えば、既存のFAQやマニュアルを基に、わずか30分程度で回答用のチャットボットのプロトタイプを作成できます。
- 作り方:
○ Difyの「ナレッジ」機能に、既存のFAQ(ExcelやPDF)をアップロード。
○ 「チャットボット」のテンプレートを選択し、アップロードしたナレッジを参照するようプロンプトを設定。
○ これだけで、社員からの質問にAIがFAQの内容を基に回答するチャットボットが完成。 - 効果:
○ 総務やIT部門への定型的な問い合わせが削減され、担当者は本来の業務に集中できます。
○ 社員は24時間いつでも、必要な情報を自己解決できるようになります。
散らばった社内PDF・Excelを“聞けば答える”ナレッジベースに
製品情報や過去のプロジェクト資料、営業ノウハウなど、社内に散在する貴重な情報資産。DifyのRAG機能を使えば、これらを「話しかければ答えてくれる」賢いデータベースに変えることができます。
- 活用例:
○ 営業支援: 過去の提案書や成功事例をDifyにKnowledgeとして学習させ、「A社に似た業種の成功事例を教えて」と質問すれば、AIが最適な資料を提示。
○ ノウハウ引継ぎ支援: ベテラン社員の残した技術文書や設計図を学習させ、若手社員が直面した課題に対するヒントをAIが提供。 - 効果:
○ 必要な情報にたどり着くまでの時間が劇的に短縮されます。
○ 属人化しがちな知識やノウハウが組織全体で共有・活用され、組織力が向上します。
メール下書き→翻訳→要約をワンクリックで自動化
海外とのやり取りが多い部署では、メールの作成や内容の把握に時間がかかりがちです。Difyの作業自動化(ワークフロー)機能を使えば、一連の作業をワンクリックで実行できるようになります。
- ワークフローの設計:
○ 「日本語で下書きを入力」
○ →「英語に翻訳」
○ →「要点を3行で要約」
○ →「下書き、翻訳文、要約をまとめて出力」
という流れを、Difyの画面上でブロックをつなぎ合わせるように設計します。 - 効果:
○ これまで手作業で行っていたコピー&ペーストや、複数のツールを往復する手間がなくなります。
○ 人的ミスが減り、コミュニケーションの質とスピードが向上します。
費用と導入準備
Difyは、利用形態に応じて柔軟なプランが用意されており、手軽に始めることができます。
クラウド版:無料枠からスタート
最も簡単な始め方は、Difyが提供するクラウドサービスを利用する方法です。
- 無料プラン(Sandbox):
○ 月200メッセージ分のクレジットが付与され、5つまでのAIアプリを構築可能。
○ まずは機能を試してみたい、小規模なテストをしたい場合に最適です。 - 有料プラン(Professional/Team):
○ 月額$59から利用可能。より多くのクレジットが付与され、構築できるアプリ数も増加。
○ 本格的な業務利用や、チームでの共同開発に適しています。
自社サーバー版(オンプレミス)
セキュリティ要件が厳しい企業向けに、自社のサーバーにDifyをインストールして利用することも可能です。オープンソースなのでソフトウェア自体の費用はかかりませんが、サーバーの構築・維持管理コストが別途必要になります。
コスト・セキュリティ・運用負荷で比較する判断基準表
| 比較項目 | クラウド版(無料・有料) | 自社サーバー版(オンプレミス) |
|---|---|---|
| 初期コスト | 低い(無料から始められる) | 高い(サーバー構築費用が必要) |
| 運用負荷 | 低い(Difyがインフラを管理) | 高い(自社での保守・運用が必要) |
| セキュリティ | Difyのセキュリティ基準に準拠 | 自社のポリシーに合わせて高度なセキュリティを構築可能 |
| おすすめ | 手軽に始めたい、多くの企業 | 機密情報を扱う、高度なセキュリティ要件がある企業 |
すぐに試す3ステップ
Difyの導入は簡単です。以下の3ステップで、今日からAIアプリ開発を始められます。
① アカウント開設とテンプレート選択
まずはDifyの公式サイトにアクセスし、メールアドレスやGoogleアカウントで無料登録します。ログイン後、「テンプレートから作成」を選び、「カスタマーサポートボット」や「記事作成アシスタント」など、自社の目的に近いテンプレートを選択してみましょう。
② 自社データを1ファイルアップして動作確認
次に、選択したテンプレートに自社のデータを組み込んでみます。例えば、社内FAQのExcelファイルを1つだけアップロードし、「ナレッジ」として設定します。その後、プレビュー画面で実際に質問を投げかけ、AIが自社の情報に基づいて回答を生成するかどうかを確認します。
③ 上司やチームへデモ共有しフィードバック取得
STEP2で作成した簡単なプロトタイプを、上司やチームメンバーに共有しましょう。Difyでは、作成したアプリのURLを簡単に共有できます。「このFAQボットがあれば、問い合わせ対応が楽になりそうだね」といった具体的なフィードバックを得ることで、本格導入に向けた社内の理解と協力を得やすくなります。
導入例でわかるDifyの効果
Difyは、その柔軟性と使いやすさから、すでに多くの企業で具体的な業務改善に繋がっています。ここでは、マーケティング、経理、そして全社的な情報共有という3つの異なるシーンにおける、Difyのリアルな活用事例を紹介します。
事例1:【マーケティング】16時間の調査が30分に!リサーチ業務の完全自動化(FLINTERS株式会社)
マーケティング戦略を立案する上で、市場調査や競合分析は不可欠ですが、その作業には膨大な時間と労力がかかります。ITコンサルティング企業のFLINTERS株式会社では、この課題をDifyで解決しました。
- 課題:特定プロダクトの現状分析(ポジショニング整理、SNSでの口コミ収集、資料化など)に、1回の作業で16時間もの時間が費やされており、分析の属人化も問題となっていました。
- Dify活用: Difyのワークフロー機能を使い、一連のリサーチ業務を自動化するAIアプリを構築。
1. 情報収集: Google検索、YouTube、SNSと連携し、競合情報や口コミを自動で収集。
2. 分析: 収集した情報をSWOT分析などのフレームワークに当てはめて自動で分析。
3. 資料化: 分析結果をGoogleスライドに自動で流し込み、レポート(商品概要、ペルソナ、ポジショニングマップ等)を生成。 - 効果:これまで16時間かかっていた作業が、わずか30分に短縮されました。担当者はキーワードとURLを指定するだけで、質の高い分析レポートを即座に入手できるようになり、退屈なコピー&ペースト作業から解放されました。これにより、担当者はより本質的な「分析の考察」や「戦略立案」に集中できるようになりました。
※出典:マーケティング戦略のための事前調査をAIで効率化!Difyを活用した成功事例を徹底解説
事例2:【経理】請求書処理の自動化で年間60%のコスト削減(株式会社Hakuhodo DY ONE)
経理部門における請求書の処理は、多くの企業で手作業が多く、時間とコストがかかる業務です。デジタル広告代理店の株式会社Hakuhodo DY ONEは、DifyとRPAツール「Power Automate」を連携させ、この課題を解決しました。
- 課題:従来のRPAロボットによる自動化は実現していたものの、請求書のフォーマット変更に伴う改修や、RPAのライセンス費用が高騰していることが新たな課題となっていました。
- Dify活用:
1. Power AutomateがOneDrive上の請求書PDFを取得。
2. DifyのワークフローAPIを呼び出し、PDFをテキスト化。
3. LLMがテキストから請求書番号、日付、金額などの必要情報を抽出。
4. 抽出した情報をJSON形式で整形し、Power AutomateがExcelに自動転記。 - 効果:Difyがオープンソースであるため、高額なRPAライセンス費用を削減し、年間で約60%のコスト削減を見込んでいます。さらに、プログラミング知識が不要なDifyとPower Automateを活用することで、経理担当者自身がフローの管理・修正を行えるようになり、開発チームへの依頼も不要に。業務を最も理解するチームが自律的に改善を進められる体制が構築されました。
※出典:Dify活用事例 請求書処理の自動化で経理業務を効率化する方法とは?
事例3:【全社】1000人規模の組織に社内チャットボットを導入(株式会社カカクコム)
従業員が増え、事業が多角化する中で、社内情報の検索や問い合わせ対応の非効率化は多くの大企業が抱える課題です。「食べログ」などを運営する株式会社カカクコムは、OSS版のDifyを自社サーバーに構築し、全社向けのチャットボットを導入しました。
- 課題:社員が1000人を超え、経費精算や出張手続きなど、社内ルールに関する問い合わせが増加。情報がどこにあるか分からず、探す手間が発生していました。
- Dify活用:
→ 汎用チャットボットの提供:まずはGPT-4oと連携した汎用的なチャットボットを全社に展開。
→ 社内ナレッジのRAG活用:次に、Confluence(社内Wiki)上の経理関連文書をDifyのナレッジベースに登録。「知識検索」機能を持つチャットボットに進化させ、社内情報に関する質問に答えられるようにしました。
→ Teamsアプリ化:社員が日常的に使うTeamsから直接チャットボットを利用できるよう、Webページを埋め込んだアプリを提供。 - 効果:
→ 年間18,000時間の業務削減:全社アンケートの結果、チャットボット利用により、年間で18,000時間もの業務時間削減効果を見込んでいます。
→ 問い合わせ15%削減:経理部門の問い合わせ対応時間を約15%削減。
→ 利用率27%向上: Teamsアプリ化により、デイリーアクティブユーザー数が27%増加。
これらの事例から分かるように、Difyは特定の部署や業務だけでなく、組織全体の生産性を向上させるポテンシャルを秘めています。
おわりに
Difyは、「AI活用を始めたいが、開発リソースが限られている」という多くの企業にとって、アイデアを具体的な形にし、実行フェーズへ踏み出すための強力な選択肢です。
専門的なプログラミング知識は不要。大切なのは、「自社のどの業務を、AIでどう改善したいか」というビジネス視点です。
この記事で紹介したように、まずは無料プランで小さなプロトタイプを作り、その成果を社内で共有することから始めてみてください。AIが実際に業務を効率化する様子を目の当たりにすれば、AI導入に対する心理的なハードルは大幅に下がり、全社的な活用の機運も高まるはずです。
HPは、ビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。
Windows 11 は、AIを活用するための理想的なプラットフォームを提供し、作業の迅速化や創造性の向上をサポートします。ユーザーは、 Windows 11 のCopilotや様々な機能を活用することで、アプリケーションやドキュメントを横断してワークフローを効率化し、生産性を高めることができます。
組織において Windows 11 を導入することで、セキュリティが強化され、生産性とコラボレーションが向上し、より直感的でパーソナライズされた体験が可能になります。セキュリティインシデントの削減、ワークフローとコラボレーションの加速、セキュリティチームとITチームの生産性向上などが期待できる Windows 11 へのアップグレードは、長期的に経済的な選択です。旧 Windows OSをご利用の場合は、AIの力を活用しビジネスをさらに前進させるために、Windows 11 の導入をご検討ください。
※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。


ハイブリッドワークに最適化された、Windows 11 Pro+HP ビジネスPC
ハイブリッドなワークプレイス向けに設計された Windows 11 Pro は、さらに効率的、シームレス、安全に働くために必要なビジネス機能と管理機能があります。HPのビジネスPCに搭載しているHP独自機能は Windows 11 で強化された機能を補完し、利便性と生産性を高めます。
詳細はこちら