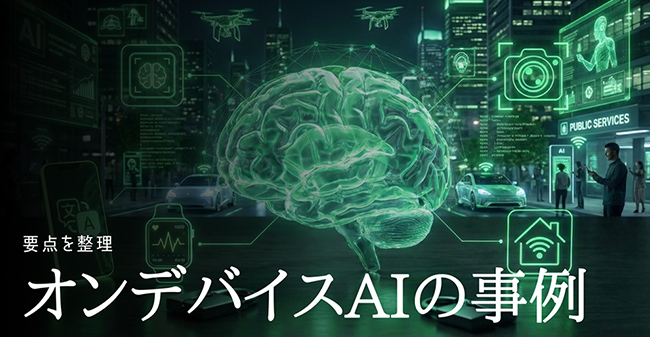AIは“どこで”動くべきか──クラウドとローカルが融合する新時代のPC
2025-11-25
マイクロソフトがAI搭載PCの新カテゴリーとして「Copilot+ PC」を発表したのは2024年5月のことでした。1年超が経過し、各社の製品ラインアップも拡充されてきています。日本HPもそのフラッグシップ機HP EliteBook X G1i 14 AI PCを筆頭に、複数の製品をラインアップしています。
ここでは、クラウドサービスとして身近な存在になった生成AIのオンデバイス利用とその共存について考えてみることにしましょう。
フリーランスライター:山田祥平
デバイスに閉じたAIが意味するもの
Copilot+ PCは、40TOPS(毎秒40兆回のAI演算性能)以上のNPU、16GBのRAM、256GB以上のSSDを搭載することを要件とし、AI機能の快適な動作を保証します。でも、クラウドサービスとしてのAIを利用するだけなら、手元のPCに高性能なAI演算性能は必要ありません。クラウドのコンピュータリソースを頼れば、40TOPSに満たないPCでも快適にAIを利用できるはずです。
Copilot+ PCが、高いAI演算性能を担保するのは、生成AIのオンデバイス利用を想定してのことです。つまり、クラウドリソースに頼らず、目の前のローカルPCに閉じた処理でセキュリティ等を担保するわけです。企業などでのAI利用では、その学習ソースに自社の機密情報を含まないと実用にならないことが多いはずです。でも、ローカルでの処理が担保されれば機密を守ることができます。
クリエイティブ分野でのAI利用においても、キビキビしたレスポンスでグラフィックスの生成や加工など、いったんクラウドに送って処理させ、結果が戻ってくるタイムラグによる煩わしさを感じさせないスムーズな処理ができることが求められます。
こうしたオンデバイスAIは、これからのAI利活用において、欠かすことができない要素になる可能性があります。Copilot+ PCは、それを見越し、その可能性を探る試みなのかもしれない。
記憶を支援するリコール
Copilot+ PCの目玉機能のひとつでもあったリコールですが、発表後、その機能は紆余曲折がありました。
「リコール」は、PC上で行ったほぼ全ての操作(ウェブサイトの閲覧、ドキュメント作成、チャットなど)を継続的に、あるいは重要なイベントが発生したタイミングでスナップショットとして記録します。
こうして記録された情報をもとに、後から「あの時見ていた情報は?」といった曖昧な記憶を頼りに過去の画面を検索できるようになります。
リコールは2024年5月のCopilot+ PC発表直後、その機能の強力さゆえに「ユーザーの全操作を記録する」という仕組みがプライバシーおよびセキュリティ上の大きな懸念を引き起こし、世界中から批判が殺到しました。この反響を受け、マイクロソフトは当初の方針を大幅に転換し、プライバシー保護を強化する複数の重要な変更を余儀なくされました。
まず、リコールはデフォルトで無効となり、ユーザーが自ら有効化を選択するオプトイン方式が採用されました。ユーザーが自ら有効にしない限りオフの状態になります。また、リコールの有効化や保存されたスナップショットの閲覧には、顔認証や指紋認証など、Windows Helloの生体認証が必須となりました。データ保護も強化され、スナップショットデータはPCローカルに暗号化して保存され、クラウドには送信されません。また、ユーザーはいつでもスナップショットの保存を一時停止したり、削除したり、機能を完全にオフにしたりできます。
これらに対応するため、リコールは2024年6月18日のCopilot+ PCの初回リリースには搭載されませんでした。
その後、数ヶ月のテストと調整期間を経て、リコール機能は2025年4月のWindowsアップデートの一環として、Copilot+ PC向けに正式に提供が開始されました。 現在、対応するPCで設定を有効にすれば、この機能を利用することができます。手元のHP EliteBook X G1i 14 AI PCでも順調に稼働中です。
セキュリティの裏に潜む、ローカルAIのジレンマ
現時点で、リコールはローカルAI処理専用の機能です。目の前のPCの40TOPS以上のNPUが、その全処理を引き受けます。社外秘やプライバシー性の高い情報が外部に漏えいする心配もありません。仮にPCが盗まれるようなことが起こり、内部のデータが解析されようとしたとしても、リコールのデータは暗号化されているため、生体認証をパスしない限り参照は困難です。
ただ、ローカルPCにのみデータを保存し、各種の検索処理などもローカルで行われることは、データの永続性とアクセス性に関わるいくつかの問題を残しています。リコールがローカルPCにのみデータを保存することは、プライバシー面では利点ですが、実用面ではいくつかの重要な問題点を抱えているからです。
まず、デバイスの故障・紛失・盗難などによって全ての「記憶」を失うリスクがあります。PC本体が唯一のデータ保管場所であるため、SSD/HDDの故障、マザーボードの破損などでPCが起動しなくなると、そこに保存されていた数ヶ月、数年分のリコールデータが完全に失われる可能性があります。
これは、全ての貴重なデータを一つのカバンに入れているのと同じで、そのカバンを落としたら全てが終わり、という状況を生み出します。
さらに、ユーザーが新しいCopilot+ PCに買い替えた際、古いPCに蓄積されたリコールのデータをシームレスに引き継ぐ簡単な方法がありません。このことによって、「記憶」は分断されます。古いPCでの作業履歴は古いPCに残り、新しいPCではまたゼロから記憶を始めることになります。クラウドサービスのように「新しいPCでサインインしたら、今までの履歴が自動で同期される」といった手軽さがないのです。
そして、今、多くのユーザーは、自宅のデスクトップPC、外出先のノートPC、場合によっては職場PCなど、複数のデバイスを使い分けています。リコールがローカル保存に限定されるため、これらのデバイスをまたいだ体験の連携が全くできません。
「昨日、ノートPCで見ていたあの資料」をデスクトップPCのリコールで探すことはできません。それぞれのPCが独立した「記憶」しか持たないことによって、リコールの利便性は大幅に損なわれています。
プライバシーやセキュリティと引き換えに、現代のコンピューティング環境で重視されるデータの可用性、永続性、そして利便性を大きく犠牲にしているとも言え、今後の可能性についての議論が求められます。
実践的パートナーとしてのHP AI Companion
HPのCopilot+ PCには、独自のAIアシスタント機能として「HP AI Companion」が搭載されています。
主な機能として、何でも質問してAIの回答が得られるアスク機能、文書類を登録するライブラリを作成しておき、それだけを情報ソースとして要約作成、レポートの下書き、翻訳などに使えるアナライズ機能、そして、AIによるPCの使用状況学習とパフォーマンスの最適化を担うパフォーム機能が提供されます。
アスク機能やライブラリ機能については、初版のリリース時にはクラウドサービスのフロントエンドにすぎませんでしたが、当初の約束通り、現在ではオンデバイスとクラウドの双方をユーザー自身がその場で切り替えることができるようになっています。
ちなみに、AI Companionを実行している生成AIのモデルは、オンデバイスではPhi-3.5、クラウドではGPT-4oを使用しています。双方ともに1日あたりのメッセージ送信回数などの制限はありません。また、利用に際しての追加費用も必要ありません。HPはこれらのモデルをいつでも変更できるように設計しています。今後、別のAIモデルに変更される可能性もあれば、より性能の高いAIに更新されることも想定されています。
また、AI Companionはユーザーの応答をモデルのトレーニングに使用しないことが保証されています。クラウド処理に使われるGPT-4oで進める会話は、モデルのトレーニングには使用されません。モデルは、さまざまなデータソースセットでトレーニングされます。オンデバイスモードの場合、全てのプロンプト、クエリ、応答が常にデバイスローカルに安全に保持されます。
もちろんオンデバイス処理はPCがインターネットに接続されていない状態でも使用可能です。HP AI Companionにサインインすると、オンデバイスモードでアスク機能が使えるほか、インターネットに接続していなくてもアプリのその他のローカル機能を使用できます。
オンデバイスのアスク機能に最新の知識はいつのものか尋ねてみたところ、「私の知識は2021年初頭の知識に基づいています。オンデバイスに関する最新情報については、直接HPの公式リソースや最新ニュースリリースを参照する必要があります。私の情報はそれらの最新情報に基づいており、2025年初頭の知識ではありません」という回答(原文のまま)が得られました。その一方でアスク機能をクラウドに切り替えて同じことを尋ねたところ、「私の知識は2023年10月時点のものになります。これ以降の情報や出来事については持っていませんので、その場合は最新の情報を確認することをおすすめします。必要な情報があればお手伝いしますので、気軽にお尋ねください!」(原文のまま)とのことでした。
まとめ
オンデバイス処理の可能性を模索するリコールと、クラウドとローカルの切り替えをコントロールする術をエンドユーザーに与えるハイブリッドサービスを提供するHP AI Companionは、それぞれが、これからのPCにおけるAI活用を模索し続けています。
まず、リコールはOSそのものに「記録」ではなく「記憶」の概念を組み込もうとしています。オンデバイスでの処理を徹底し、人間の記憶の曖昧さをPCが完全に補完することを目指しています。つまり、PCそのものを人間のコンパニオンにするチャレンジです。
その一方で、HP AI Companionはユーザーに寄り添う「実践的パートナー」です。オンデバイスモードとクラウドモードをユーザーが意図を持って切り替えられるように設計され、その切り替え方法も明確です。
両者は競合するというよりも、目指す方向性や役割が異なる存在です。リコールがPCの「あるべき姿」を根本から問い直す長期的で壮大なビジョンであるのに対して、HP AI Companionは、今日のユーザーが直面する課題を解決するための現実的で実践的なソリューションです。
どちらもこれからのAI PC時代を象徴する重要な機能であり、この2つのアプローチが今後どのように進化し、融合していくのか、とても楽しみです。
HPは、ビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします。
Windows 11 は、AIを活用するための理想的なプラットフォームを提供し、作業の迅速化や創造性の向上をサポートします。ユーザーは、 Windows 11 のCopilotや様々な機能を活用することで、アプリケーションやドキュメントを横断してワークフローを効率化し、生産性を高めることができます。
組織において Windows 11 を導入することで、セキュリティが強化され、生産性とコラボレーションが向上し、より直感的でパーソナライズされた体験が可能になります。セキュリティインシデントの削減、ワークフローとコラボレーションの加速、セキュリティチームとITチームの生産性向上などが期待できる Windows 11 へのアップグレードは、長期的に経済的な選択です。旧 Windows OSをご利用の場合は、AIの力を活用しビジネスをさらに前進させるために、Windows 11 の導入をご検討ください。
※このコンテンツには日本HPの公式見解を示さないものが一部含まれます。また、日本HPのサポート範囲に含まれない内容や、日本HPが推奨する使い方ではないケースが含まれている可能性があります。
また、コンテンツ中の固有名詞は、一般に各社の商標または登録商標ですが、必ずしも「™」や「®」といった商標表示が付記されていません。


ハイブリッドワークに最適化された、Windows 11 Pro+HP ビジネスPC
ハイブリッドなワークプレイス向けに設計された Windows 11 Pro は、さらに効率的、シームレス、安全に働くために必要なビジネス機能と管理機能があります。HPのビジネスPCに搭載しているHP独自機能は Windows 11 で強化された機能を補完し、利便性と生産性を高めます。
詳細はこちら